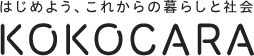「取れすぎて困る」鮭の黄金期
――地球温暖化をはじめとするさまざまな影響によって鮭の不漁が続いていますが、内藤さんが漁協に入られたころはどうだったのでしょうか。
内藤智明さん(以下、内藤) 実家は昭和48年(1973年)から鮭の定置網漁業を営んでいました。私が野付漁協に勤め始めて間もない、1980年代後半から北海道の鮭は黄金期を迎え、9月に漁が解禁されると、秋鮭がどんどん上がってくる状況でしたね。北海道全体で年に18万トンから20万トンもの漁獲量があったんですよ。
佐藤友美子さん(以下、佐藤) 尾数でいうとどのくらいですか?

豊洲市場で魚を仕入れ店先に到着した佐藤さん(写真=疋田千里)
内藤 だいたい定置網の1漁場で、5万尾ぐらいです。
佐藤 キロ(Kg)単価はどのくらいですか?
内藤 秋鮭は大衆魚といわれていて、雄・雌込みの価格が1キロ150円ほど。「大漁貧乏」といわれる値段で、鮭1本と100円の缶ジュース1本を交換だ、なんていう話が冗談抜きでなされたくらいの価値でした。今じゃありえない話です。

野付漁協の内藤智明さん
佐藤 えぇぇ! 150円は安すぎますね。私が仕事を始めたころは、年末になると鮭の入った木箱が天井に届くくらいまである状態が毎日続いていました。贈り物に鮭が選ばれていた時代で、鮭のサイズが総じて今よりワンランク大きかったですね。北海道では鮭が取れすぎていた時代には海外に輸出していたという話も聞いたのですが、実際はどうだったのでしょう?
内藤 15万トン以上取れていたときは、国内のマーケットだけでは消費し切れなかったので、一時中国に輸出した時期もありました。今は国内需要をまかなうのも大変な状況です。
上がり続ける鮭の価格
――黄金期が過ぎて、2010年ころからはだんだんと漁獲量が減少していったそうですね。
内藤 2020年代に入ってからはさらに深刻化していて、2024年の北海道の秋鮭の全体の漁獲量は4万4千トンまで落ち込みました。2025年の今年の回帰予想は3万トンを割るのではないかともいわれている状況です。昨年の浜値がキロ単価980円ですから、18万トン取れていた時代からすると、価格は6倍以上です。
佐藤 私は約35年間築地で鮭を扱っているのですが、築地でも鮭の在り方が変わりました。一体今年はいくらになるのかと心配しています。

塩蔵された鮭を切り身にするのが、佐藤さんの日課(写真=疋田千里)
内藤 価格は需要と供給のバランスで決まるので、漁獲量が減れば価格は高くなります。ただ、昨年の価格が天井価格だと個人的には思っているし、思いたい。ここ10数年間、販売価格が高くなりすぎないように一商品あたりの数量を減らして単価を下げていますが、浜の人間からするとじくじたる思いがある。やっぱりおいしく、たくさん食べてもらいたいですから。
佐藤 うちの例でいうと、お歳暮で鮭を使っていたかたが、これまでと同じ目方では予算オーバーしてしまうと困っていました。
内藤 昔は鮭といえば新巻き鮭で、一尾丸ごと贈るスタイルが主流でしたが、今は1尾贈られても困る方が増えていますよね。魚屋さんに持って行って、半分は切ってもらうお礼に置いてくるという話も聞きました。今は切り身を真空パックして贈る時代です。
佐藤 そう、業者への販売でも、真空パックが常識になりました。
内藤 包装スタイルそのものがガラッと変わりましたよね。昔は取れたてに塩をして、冷凍したものを貨物列車で築地に送っていましたから。
佐藤 貨車で揺られて市場に来る間に塩がなじんで熟成するから、「昔の鮭はおいしかった」という話を先輩がたから聞いたことがあります。
内藤 「山漬け」のことですね。塩漬けにした鮭を積み上げて、25キロの塩袋をおもしにして作っていました。

野付漁協では現在も、山漬け製法の流れをくむ商品を製造している(写真=編集部)
――現在は、鮭の身に直接塩分を注入するインジェクション加工が主流となっています。
内藤 スローフードの時代で山漬けが注目されたこともありましたが、今はうちの商品もほとんどがインジェクションです。
佐藤 私の店では山漬けも売っていますが、減塩志向の今の時代、売ることの難しさを実感しています。しょっぱさが季節で変化することも、難しさに拍車をかけます。塩味は徐々に徐々に鮭の身にしみ込んでいくため、漬け込んでからすぐの年末ごろは塩が甘いと言われ、月日がたつと、今度はしょっぱいと言われてしまうんです。夏は暑いからしょっぱい鮭がちょうどいいとお伝えしても、濃くて食べられないというかたもいます。
市場では加工の仕方や塩蔵した鮭の熟成のおいしさなどを対面でお伝えできますが、スーパーなどでは難しい。だから一定の味を保つためにインジェクションが主流になっているのには納得しています。けれど、変わっていく面白さも楽しんでほしいなぁとは思いますね。

写真=疋田千里
いくら努力をしても鮭は戻ってこない
――野付漁協さんでは、産地として漁獲量回復のためにどのような努力をされているのでしょうか?
内藤 北海道では各浜から鮭の稚魚を毎年10億尾放流しています。野付を含む根室管内だけでも2億尾放流しているんですよ。放流する尾数は何年も変わっていませんが、地球温暖化の影響で海水温が4~5℃も上がるような状況もあってか、回帰率はかなり落ちています。ならばと、放流する尾数を増やそうと思いたくなるものですが、ふ化場のふ化能力はすでに目一杯。もう増やせないというのが現実です。
――鮭の卵は、どのように確保されているのでしょうか?
内藤 その話の前に、近年の定置網漁の話をさせてください。野付漁協があるのは、北海道の東側に当たる根室管内。かつては鮭の水揚げ高が北海道で一番でした。漁法は定置網漁で、9月の前期群、10月の中期群、11月の後期群と3か月にわたって鮭を水揚げしてきています。

野付漁協より海を望む(写真=豊島正直)
しかし現在は9月の下旬から10月の第1週に前期群と中期群が入り交じるような感じで、11月に入るとほとんど終了。3か月あった漁期が今は実質2か月になっています。鮭は9月1日から漁獲が許可されているのですが、ここ数年は1週間から10日、漁の開始を遅らせています。これによって河川に遡上する鮭を増やし、ふ化事業用の卵を確保しているのです。
――そこまで自分たちで行っているのですね。
内藤 かなり前は国営でサケ・マスのふ化放流事業をやっていましたが、今は民間に移行されています。ふ化場の運営は漁師などの漁業事業者が水揚げ金額の8%を増殖付加金として捻出し、集めたお金で行われているんです。漁師や私たち漁協もやれるだけの努力はしているものの、回帰率は上がりません。さらに全体的にサイズも小さくなっていて、今は平均2.7キロ。かつて定番サイズだった、4キロを超える鮭にはめったにお目にかかれなくなっています。
佐藤 あまり大きく育たないのはなぜなのでしょう?
内藤 私はえさ不足ではないかと考えています。海の環境が大きく変わっている証拠ともいえるかもしれません。稚魚の放流も雪と河川の氷が落ちる3月の下旬が主流でしたが、今はもう少し大きくしてからにするなど、試行錯誤を繰り返しています。
鮭の稚魚はなぎさ帯をずっと伝い、適水温になると沖合に出て大海の方に向かうことは分かっているので、それに合わせて放流時期を見直すことなどもしています。ですが、それ以上に地球温暖化で海水温が高くなってしまい、どの程度の割合が北太平洋、ベーリング海、アラスカあたりまでたどり着いているのか……。自然界のことなので全く読めない状況です。
佐藤 鮭の漁獲値の南限が、どんどん北へ移行しています。本州の漁獲地でも、それぞれに伝統的な製法が守り伝えられてきているのに、鮭が取れなければ食文化も途絶えてしまいますね。

産地を訪ねた際の佐藤さん(写真提供=佐藤友美子さん)
内藤 その原料確保のために、他地域の業者も北海道へ買い付けに入ってきます。北海道の価格相場が高騰する背景には、こういった事情も影響しています。
――海外から輸入される鮭や養殖についてはどのように思われていますか?
内藤 需要と供給のバランスですよね。チリ産の銀鮭やノルウェー産のトラウトの価格が、秋鮭の価格の指標の一つになっているのは事実です。15万トン、20万トン水揚げされていたときには、輸入の鮭はあんまり入ってこないほうがいいなと思っていましたが、今はそんなことは言っていられません。
佐藤 ここ数年は、全国で鮭の養殖も盛んになってきていますが、それについてはどうご覧になっているのですか?
内藤 三陸の銀鮭のようなボリュームのある数量になると意識しますが、ご当地サーモンといった生食主体のものは、私たちの鮭とは別物だと考えています。昨年8月には養殖施設を見学して話を伺いましたが、採算ラインに乗せるのも大変そうだなと思ったのが、素直な感想です。
時代や国が変わっても
――場内市場が築地から豊洲に移って7年。最近の築地場外はどんなようすでしょうか?
佐藤 私はこれまで築地の先輩に聞いたり、釧路、根室、猿払などの産地を訪ね、話し、体験したことで、鮭を取り扱えるようになりました。今度、野付漁協さんにも伺いたいです。
内藤 ぜひお越しください。10月あたりだったら鮭漁も見ていただけると思いますよ。
佐藤 築地場外はインバウンドに沸いて大変なことになっていますよ。店頭で販売している鮭のおにぎりを買うかたの80%は外国のかた。鮭は日本人にとって特別な魚と思っている一方で、外国の方も鮭のおいしさを分かってくださっているんだな、と令和の築地で感じています。

おにぎりの具にはたらこもあるが、一番人気は鮭だそう(写真=疋田千里)
――定番の秋鮭のほかには今、どんなものが売れていますか?
佐藤 カナダで塩蔵するとてもしょっぱい鮭があるのですが、秋田で昔から食べられている「ぼだっこ」というしょっぱい鮭と共通する部分があるようで、探し求めて来てくださる若いかたが一定数います。焼くと塩を吹くほどしょっぱい鮭です、減塩ブームで敬遠されるかと思いきや不思議なものですね。

紅鮭と秋鮭をダブルで使用。見た目もうまみも華やぐ(写真=疋田千里)
毎日食べても飽きない鮭を守るために
――ちなみにお二人は、いつの時期の鮭がいちばん好きですか?
内藤 10月ぐらいに取れる、まだ身がピンクなブナ系の大きい鮭が好きです。4キロぐらいの鮭が水揚げされると、塩蔵して食べたらおいしいだろうなぁと想像します。熟成させて天日に干して、赤みが増してきたら焼いて食べる。切り身がいちばん好きです。
佐藤 気温が違うので、東京で作り方をまねしてもおいしくできないんですよね。
内藤 ははは。鮭は北海道の浜風に当たっておいしくなるんです。
佐藤 干したり、飯ずしにしたりといろいろ作ってみましたが、地元のかたのようにはできなくて。やっぱり実際に行くしかないなと(笑)。私が好きな食べ方は、やっぱりおにぎりです。毎日店頭で鮭のおにぎりを売っているのですが、秋鮭にすごくしょっぱい紅鮭を少し混ぜて味の濃淡をつけたり、山菜やお漬物、旬の食材を合わせたりと、おにぎり一つとってもいろいろな楽しみ方があります。毎日お昼に食べているのですが、何年食べ続けても飽きません。

野付漁協近くで作られていた、漁師の鮭トバ(写真=編集部)
――生産者である野付漁協さん、販売者の佐藤さん、生活者が一体となってできることはあるでしょうか?
内藤 今はホタテが北海道の水産物では一番の水揚げで主力になっていますが、元は鮭のほうが上だったという思いがあるんです。ホタテもグローバル商材として突出した価格になってしまっていますが、今後は鮭も例外ではないかもしれない。私たちとしては金もうけを願っているわけではなくて、漁師や加工業者が再生産可能な価格で流通できればいいと思っています。だれかだけに利があるのではなく、佐藤さんのような小売店や生協さんなどを通じて消費者のみなさんに買って食べ続けてもらいたいというのが、私の今の一番の願いです。

写真=編集部
佐藤 今、私は秋鮭がいちばんおいしくて、毎日食べられることが幸せです。生協さんでも秋鮭が1年を通して食べられますよね。お子さんにもしっかり食べてもらって、その味を記憶に刻んでほしいなと思います。小さいころからおいしい秋鮭を食べられるお子さんがうらやましいです。
商いの目線で考えれば、近年は秋が近づくころに、「今年の鮭はいくらだろう」と心配することが続いています。私も、価格が原因で長年食べてくれていたお客様が離れていくのはとても不本意ですし、寂しさがあります。それぞれの立場で努力は必要ですが、努力の裏でだれかが苦しむような状況を作ってはいけないので、お互いに情報交換していくことが必要だと思います。後はやっぱり、こうやって顔を突き合わせて知り合いになることが一番ですよね。そこから何かが生まれればいいなと思います。

海外からの旅行者対応もお手のもの(写真=疋田千里)