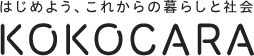繰り返し使える自然素材のラップ
ここ数年、海外から始まって日本でも注目されている「みつろうエコラップ」は、コットンの布にみつろう(みつばちが巣を作るために分泌するろう)、ココナツオイルなどをしみ込ませた自然素材の布ラップのこと。何度も繰り返し使えて、環境負荷が少ないと関心を集めている。

写真=疋田千里
程良い粘着性があり、お皿や容器にカバーをしたり、常温のおにぎりやサンドイッチを包んだり、野菜や果物を包んで冷蔵保存したりと、さまざまな使い方で活躍する。プラスチック製ラップの使用量を減らせるだけでなく、何といっても色や柄のバリエーションが豊富で、使うのが楽しくなるようなビジュアルも大きな魅力だ。

使い方はいろいろ(写真提供=藤岡亜美)
このみつろうエコラップ、日本では既製品も販売されているが輸入品がほとんど。気にはなるものの……とためらっていたら、なんと自分でも作ることができるという。さっそく、パルシステム東京(東京都新宿区)で7月に開催された「友産友消ワークショップ~ミツロウエコラップをつくろう」(※1)のようすをのぞいてみた。
※1:生活協同組合パルシステム東京、スローウォーターカフェ有限会社が共催。
ワクワクしながら「脱プラスチック」
「みつろうエコラップの作り方はとっても簡単。材料も身近で手に入るものばかりです。今日、作り方を覚えたら、ぜひ次は皆さんが講師になって周りの人に広めてください」と話すのは、講師の藤岡亜美さん。ワークショップには会場が埋まるほどの参加者が集まっていて、関心の高さが伝わってくる。

藤岡亜美さん(写真=疋田千里)
南米・エクアドルとのフェアトレードを行う「スローウォーターカフェ有限会社」の代表でもある藤岡さんは、現在は家族で宮崎に暮らし、地域の森林再生に取り組んでいる。日本みつばちの養蜂もしていて、今回のワークショップで使うみつろうは子どもたちと一緒に採ったものだ。

子どもたちとみつばちの巣を採取(写真提供=藤岡亜美)
「家の近くに海があるのですが、台風のたびにプラスチックごみが打ち寄せるんです。子どもたちと清掃しても、毎回大量のごみが集まってくる。日本は、人口一人当たりのプラスチック容器包装廃棄量が世界で2番目に多い国(※2)。まずは使い捨てプラスチックの使用量を減らさないと。みつろうエコラップは、その手段の一つです。子どもと一緒に作れるし、プレゼントしても喜ばれる。おしゃれだし、楽しみながら『脱プラスチック』できるのがいいですよね」と藤岡さん。
※2:国連環境計画(UNEP)2014年調べ。
簡単に作れて、バリエーション豊か
「みつろうエコラップ」に使う材料は、みつろう、松やに、ココナツオイル、布、といたってシンプル。藤岡さんは環境のことを考えて、布もオーガニックコットンを選ぶことをすすめている。

材料の布、松やに、みつろう、ココナツオイル(写真=疋田千里)
「みつろうエコラップを使ったことのある人はいますか?」と藤岡さんが質問すると、会場にいた数名が手を挙げた。「使ったことはないけど気になっていた」という人も。「自分で手作りできたら楽しそう」「地球のことを考えて、できることから始めたくて」と参加の理由はさまざまだ。
「まずは好きな布を選んでくださいね」と藤岡さんがテーブルに並べたのは、ピンキングばさみでカットされた、えんじ色やあい色のカラフルな布。「わあ、きれい!」「うーん、どっちがいいかな」と、さっそく盛り上がる。毎日のように使うものだからこそ、好きな色や柄で作ったらきっと楽しいに違いない。
「今回は無地の布ですが、柄の布で作ってもかわいいですよ。丸く切ってもいいし、大きさも形も自由です」と藤岡さん。自分のセンスやスタイルを生かせるのが手作りの魅力だ。

色や形を変えるとさらに楽しい(写真提供=藤岡亜美)
使う布はハンカチのような薄手のものがおすすめだという。家で作る際には、環境に配慮した洗剤で洗ってのりを落とし、アイロンをかけておく。
作業は、まるでチーズのようなみつろうの塊を、チーズおろし器や野菜のスライサーなどを使って薄く削るところからスタート。やってみると、これが意外と硬い! スライサーを傾けたり、力加減を変えたり……工夫しているうちにだんだんとコツがつかめてくる。「交代しましょうか?」「こうやるといいですよ」と、一緒に手を動かしているうちに参加者同士の会話も弾む。

写真=疋田千里
「これだけ!? 簡単にできた!」
さて、分量どおりにみつろうを削ったら、180~200℃に温めたホットプレートに布より大きくカットしたクッキングペーパーを置き、その上に布を載せる。「ホットプレートでなくても、フライパンやアイロンでも簡単にできます」と藤岡さん。

写真=疋田千里

写真=疋田千里
削ったみつろう、松やに、ココナツオイルを布の上にちりばめるように載せたら、全部がちゃんと溶けるのを待つ。ホットプレートからジュウジュウという音が、何だかお好み焼きのようだ。違うのは、みつろうやココナツオイルの優しいにおいが、ふわっと漂ってくること。
3種類の油脂が溶けたらホットプレートは保温にして、動物の毛を使ったはけで布の中心から外側に向かってむらなくしみ込むように広げていく。熱いのでピンセットを使って布の端を持ち上げて引っ繰り返し、表・裏・表と3回同じようにはけで油脂を広げる作業を繰り返す。「端まで駆け抜けるように“シュッ!”とはけを走らせる」のがコツだ。

写真=疋田千里
油脂がなじんだら、ピンセットで布を持ち上げたまま待つこと少し。油脂が冷えて固まったら、もう完成だ。「これだけ!? 簡単!」と参加者もびっくり。作り方は簡単でも、自分で作ったと思うと何とも言えない愛着がわいてくる。完成した一枚を手にした参加者からはうれしそうな笑顔がこぼれていた。

写真=疋田千里

写真=疋田千里
みつろうエコラップを触ってみると、ふにゃっと軟らかく不思議な感触。温度が高いと軟らかく、低いとやや硬く変化する。容器のカバーとして使う場合には、手の温度で少し温めながら布と容器の端を押さえると密着しやすい。

写真=疋田千里
「気持ちいい手触りでしょう? 最初は少しベタベタした感じがするかもしれませんが、使っていくうちになじんできますよ」と藤岡さん。
ホットプレートや道具にみつろうや油脂がついてしまったときは、60℃以上のお湯でよく洗い落とす。すりおろし器やはけなどについた油脂は落とし切るのが難しいので、みつろうエコラップ作り専用に用意するのがおすすめだ。
大事に使ったら、最後は土に返る
みつろうエコラップを長く使うために、気をつけたいポイントがある。まず、みつろうは60℃以上で溶けてしまうので高熱に弱い。電子レンジや高温のものに使うのはNGだ。また、レモンやパイナップルなど強い酸性のもの、生魚や生肉、においが強いものに使うのは避けたほうがいい。
「それさえ気をつければ大丈夫! 大事に使えば1年くらいは洗って繰り返し使えますよ」。藤岡さんは、サンドイッチを包んで子どものお弁当箱代わりにしたり、アウトドアに持っていったり、お菓子をラッピングしてプレゼントしたりと、いろいろな場面で使っていると話す。

写真=疋田千里
お手入れの際は、水やぬるま湯で洗ってから、直射日光を当てずに風通しがよいところで自然乾燥させる。環境に配慮した洗剤を使う場合にも、なるべく薄めてから洗いたい。藤岡さんの家では、十分に使い終わったら、最後は畑に埋めているのだという。「全部、土に返る素材ですから」
「エコラップは一つのきっかけ。これを、使い捨てではない暮らしを始める入口にしてほしい」と藤岡さん。

写真=疋田千里
藤岡さんが近くの海で目にしたように、今、世界の海には合計で1億5,000万トンものプラスチックごみが存在しているといわれている。さらに、そこに毎年800万トンもの新たなプラスチックごみが流入しているのだ(※3)。とくに深刻なのは「使い捨てプラスチック」の多さ。
「このままだと2050年には、海のプラスチックごみが魚の量を超えてしまうそうです。海を見るたびに、使い捨てやビニール製品の使用を減らそうと思うし、エコラップの魅力や手作りの楽しさを伝えて、友だちになった人たちと一緒にプラスティックに頼らない暮らしを広めていきたいです」と藤岡さん。
エクアドルの村から学んだこと
藤岡さんは、フェアトレードの会社「スローウォーターカフェ」を立ち上げ、学生時代から通っていたエクアドルのチョコレートやサイザル麻製品を扱ってきた。その生産者たちの暮らしから、自分たちの足元にある素材を使って、何でも手作りすることの素晴らしさを学んだという。

スローウォーターカフェで扱うサイザル麻のバッグ(写真提供=藤岡亜美)

ワークショップでバッグの作り方を練習し合う女性たち(写真提供=藤岡亜美)
「わたしが通っているエクアドルの村は、1990年代に鉱山開発されそうになった場所なんです。開発を受け入れればお金が入って、村に学校や診療所ができますよと言われたのに、村の人たちは話し合って、開発をせずに森や川を守り続けることを選びました。そのことが、わたしにはとても衝撃的でした」

伝統的なパナマ帽を手作業で編む生産者(写真提供=藤岡亜美)
町から離れた不便な場所にあって、現金収入も少ない村人たちが、どうして森や川を守ることを選択できたのか――それは、村人がお互いのコミュニケーションに多くの時間を割き、それぞれが違う作物を植えて交換し合う暮らし方に理由があるのではないかと藤岡さんは考えたという。
「足元にある素材を使って、自分たちの手で物を作り、それを村人同士で交換する。経済がコミュニティの中でちゃんと成り立っていることが、自分たちの基準で未来を選ぶためのカギだと思ったんです」

写真=疋田千里
村の女性たちは「日本のように便利なものはないけれど、わたしたちの村には汚染されていないきれいな水と空気、子どもたちがすくすくと成長できる環境がある。それだけで十分」と話していたという。
「みんなで作る暮らし」を目指して
さらに、エコラップの材料である「みつろう」を作るみつばちの文化も、藤岡さんが伝えていきたいと思っているものの一つだ。
「今わたしが宮崎で日本みつばちを飼っているのも、エクアドルの生産者さんの影響なんです。はちは半径2キロ内にあるいろいろな花からみつを集めてきます。みつばちが受粉を手伝わなければ、世界中の多くの野菜・果物は実ることができません。そのみつばちとバランスよく共生することで、人間はみつろうを使うことができる。それってすごいことですよね」

みつばちの巣を取り出す(写真提供=藤岡亜美)
「今、世界中でみつばちの数が減っています。農薬に敏感なみつばちは、『環境のバロメーター』といわれる存在。みつばちを守ろうと思えば、農薬を減らすことにもつながる。それはすべての生態系を守ることにもなります。こうしたストーリーも、みつろうエコラップと一緒に知ってほしい」

みつばちの巣(写真提供=藤岡亜美)
日本でも「みんなで作る暮らし」を目指したいと考えている藤岡さん。今、仲間たちと一緒に広げようとしているのが「友産友消」のムーブメントだ。
「みんなが自給自足を目指すのは大変だけど、『友産友消』で友達や顔の見える関係の中で作ったものを交換し合えたら、もっと暮らしは楽しく豊かになると思う。野菜でもいいし、料理でもいいし、何か得意なことでもいい。みつろうエコラップもそんな『友産友消』の一つです。みつろうエコラップをだれかと一緒に作ってもいいし、プレゼントしてもいい。そこから、きっといろんな輪が広がっていくと思いますよ!」