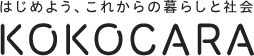大人が作ってきた制度、仕組みの中で、模索する若者たち
――大学生のときから、能條さんは「若者の政治参加」について、多方面で発言をされてきました。
能條桃子(以下、能條) 当時の私、むちゃくちゃ怒っていましたね。ジェンダーギャップも、気候変動も、資本主義構造も、上の世代が作った制度や仕組みなのに、「私たちの世代に問題が丸投げされている気がする」って。
――怒って当然だと思いました。上の世代にちゃんと言わないと、「りっぱな若者だ。日本の未来はきみたちに任せる」と丸投げされますから。
能條 投票率の低さ注釈を見て、「若者は政治に無関心だ」と批判する上の世代の人もいます。でも、若い世代が投票に行かないのには、上の世代にも責任があると思います。そもそも若い候補者が、ほとんどいないじゃないですか。若者の低投票率の原因は、大人が作ってきた制度や仕組みにこそあるはずです。
ただ、学生の頃と比べると、考え方が少し変わってきました。20代後半になって、むしろ自分こそが大人の側で、今の社会を作っている一部だと気づいたんです。だから今は怒りより、寛容な気持ちのほうが大きい。「世代を超えて手を取り合い、みんなで頑張るしかないっしょ!」と。
――能條さんが一般社団法人NO YOUTH NO JAPAN注釈を立ち上げたのは2019年、現役の大学生のときでした。
能條 21歳で団体を立ち上げ、6年たちました。学生から社会人になりましたが、活動内容は大きく変わっていません。そのかわり、覚悟や決意のようなものが深まりました。「次の世代の若者に、私たちは何を残せるのか」といつも考えています。
同じ20代でも、現役の学生だった私が話すことと、今の私が学生について話すことでは、そもそも当事者性が異なります。たとえ2、3歳の差でも、抱える困難や社会に対する問題意識は違いますから。

写真=持城壮
忖度して、ただ沈黙するだけでは、「中立」は実現できない
――NO YOUTH NO JAPANは、Instagramによる情報発信、立候補年齢注釈引き下げの運動、若い世代の政治意識に関する調査など、政治とU30(アンダーサーティー)世代を近づけるアプローチをされています。
能條 「参加型デモクラシーをカルチャーに」を理念に掲げています。特定の政党や候補者を応援したり、批判することはありません。政治に関心のない人たちに、正しい情報を伝え、政治参加への初めの一歩を提供する。「民主主義の生態系」といえるかもしれません。
政治参加は、投票行動だけではありません。立候補する、ボランティアで選挙活動を応援するなど、できることはいろいろあります。立候補年齢の引き下げについては、団体として法改正を強く訴えています。
――若い世代の政治に対する距離感は感じますか?
能條 NO YOUTH NO JAPANを立ち上げたころに比べると、むしろ縮まっている気がします。政治に対するアクティブな活動が次々と生まれていますし、政策提言する若い人のグループも増えました。
私自身、賛同できない理念や政策を掲げる団体もありますが、若者と政治との距離感が縮まるのは、悪いことではないはずです。
――2022年には、一般社団法人NewScene注釈を立ち上げ、政治分野でのジェンダー平等を実現するFIFTYS PROJECTがスタートしました。若い世代の議員だけでなく、女性議員が少ないのも、日本の現実です。
能條 FIFTYS PROJECTでは、ジェンダーギャップの解消や選択的夫婦別姓の実現などを掲げています。「政治的中立ではない」との批判を受けるかもしれませんが、中立のために忖度して沈黙するのではなく、声を上げる。「消極的中立」「積極的中立」と、私たちは呼んでいます。

政治分野のジェンダー平等を目指して、能條さんは積極的に発信を続けている(写真提供=NO YOUTH NO JAPAN)
ポピュリズムと「保守対保守」の政治構造への危惧
――それぞれの感性と考え方で、政治に声を上げる。むしろそこに、弊害はありませんか? SNSが持つ危険性、悪質なデマの拡散など……。
能條 そこは私も懸念を感じています。選挙が、社会の中でたまったうっぷんを晴らす手段になっている。みんなが余裕のない社会の中で、不安や不満を極端な差別、排外主義につなげてしまう。それで政治参加した気になるのは、とても危険です。
ポピュリズム注釈の定義について、仲間と話す機会があったんです。外に敵を作ることで、「今の社会が悪い原因は、この人たちのせいだ」と納得してしまう。それがポピュリズムにつながってしまう。社会的に脆弱な立場な人たちを追い込んでいくような言論は不健全だし、そこにどう対抗できるのか、常々考えているところです。
――「○○に投票するなんて、信じられない」と困惑するだけで、そこで思考が止まっているリベラル支持層も少なくない気がします。
能條 野党やリベラル派と相入れない政党、主義主張を支持する人たちを、「物を知らない」「リテラシーがない」と批判することには、違和感を覚えます。特に若い人たちは、魅力的だと思う政党や候補者に投票します。それはSNS戦略にたけている、といった表面的な理由だけではないと思います。
「私たちのための政策」と若者が思えるようなメッセージを、野党やリベラル派の側が出せていない。だから、これまでにない価値観、政策を打ち出す政党や候補者が出てくると魅力的に見えてしまう。
今の若い人たちは、新自由主義(ネオリベラリズム)注釈の中で育てられてきたので、その考え方が響くのも当たり前です。このままだと、リベラルな主義主張を訴える政党が消え、「保守対保守」みたいな政治構造にしかならない。そこは危惧します。

写真=photoAC
資本主義のオルタナティブとしての「協同組合」
――投票率のアップと、メディアやネットリテラシーの関係について、どうお考えですか?
能條 有権者のリテラシーについては、ファクト(事実)ベースで話すことがまず前提としてあります。正しい情報がないと、リテラシーを持って自分で考えることも、相手と話すこともできません。多面的な情報を発信するにしても、ファクトを提供することが問われます。ウェブメディアや私たちの団体の役割も、そこにありますよね。
一人一人がリテラシーを持つためには、プラットフォーマー注釈の責任も問われるべきです。例えば、X(エックス/旧Twitter)には、だれかがデマを発信しても、別の視点があることを提示するコミュニティノート注釈があります。
リテラシーを持つことが大切な反面、それは個人だけの問題か、とも感じます。陰謀論や極端な主義主張を信じ込む人を批判したり、拒絶するだけで果たしていいのか。
――「関わりたくないから、SNSでブロックしちゃえ」みたいな。
能條 地域コミュニティで孤立したり、家族と疎遠になったり、社会の中で役割がないと感じて苦しむ人たちが、極端な考え方にすがっているのではないか。そうした見方もできます。
家族、友人、同僚、近所の人などと何らかのつながりがあれば、そう簡単に極端な思想に揺れ動かされないと思うんです。そこは、協同組合の責任であり役割のような気がします。
――今年は国際協同組合年注釈にあたります。協同組合の理念や存在価値は、もっと積極的にアピールしていくべきだと思います。知ってる人は知ってる、みたいな状況も否めないので。
能條 協同組合には、すごく可能性を感じているんです。たとえば生産者の声をダイレクトに聞くことができるのは、生協(生活協同組合)の良さだし、強みです。防災とまち作りの視点に立っても、協同組合は地域コミュニティの原動力となるはずです。
ワーカーズコープ注釈を含め、「自分たちのことは自分たちで決める」という姿勢は、資本主義のオルタナティブ(代替案)として希望が持てます。NPO法人や社会的起業といった動きとは別に、若い世代が協同組合を立ち上げる動きが、もっとあってもいいですよね。

私たちは何を指標に「判断」していけばよいのだろう(写真=photoAC)
被爆国、日本。被害と加害、それぞれの歴史
――能條さんが切実に感じている社会問題、関心のあるテーマがあれば教えてください。
能條 学生時代からジェンダー平等や気候変動対策に関心があり、性暴力被害者のサポートにも、個人的に取り組んでいます。それとは別に、今も続くパレスチナを舞台とする戦争に接しながら、新たな問題意識が芽生えました。
デンマークに留学していたときの学びは大きかったし、今の活動につながっています。でもそれは、日本を含む欧米列強の枠組みの中での考え方だと、パレスチナの問題があって気づかされたんです。植民地支配の歴史も、その一つです。
すごくショックだったのが、2024年8月9日の長崎の平和祈念式典です。長崎市長がイスラエルの駐日大使を招待しなかったため、イスラエルを支援する欧米の駐日大使らが式典を欠席注釈しました。前の年に広島で開かれたG7サミットで、あれだけ「核なき世界を」と訴えていたのに……。
――被爆国である日本にも、戦争被害と戦争加害、両方の側面があります。
能條 同世代のデンマークの友人と話すと、気候変動に対してラディカルな視点を持っているのに、原発賛成派だったりする。核や放射能にまつわる情報の受け止め方が、私と全然違うんです。
広島、長崎、ビキニ環礁、福島と日本は核の被害を受けています。私の祖母や大叔母は長崎で被爆していて、幸いにも元気なので近々インタビューしようと考えています。
一方でアジア諸国への侵略と植民地支配、慰安婦や朝鮮人強制連行の問題、沖縄戦と戦後の基地問題など、被害者だけではない視点もあります。核にまつわる日本の歴史、加害の歴史を自分なりにまとめて、海外に発信していきたいと考えています。

能條さんは投票行動の尊さを重視するからこそ、一票を重く受け止めすぎないことを訴える(写真=持城壮)
選挙は「正解」を選ぶものではない
――最後に一票の重さ、投票行動の尊さについて、考えを聞かせてください。
能條 選挙は「正解」を選ぶものではないはずです。一人一人が今、ベストだと思える候補者に一票を投じる。「適当に投票するのは問題」と批判する人もいますが、一票をあまり重く捉え過ぎないことが大事ではないでしょうか。
「正しく投票する能力」や「選挙のために考えた時間」は関係ありません。ポスターの顔写真で投票を決めてもいい。
――それで決めていいんですか?
能條 政治に無関心で、選挙に行かないよりはいい。一票を棄権するより、「今度の選挙、行こう」という人が増えることのほうが大事だと思います。
たとえポスターの顔写真で投票を決めたとしても、次の選挙では「今度は政策で決めよう」と考えるかもしれません。投票所に行く。一票を投じる。その中で政治への向き合い方も変わっていく。
一過性のブームで投票率がいきなり90%になるより、毎回数%ずつでもアップするほうが、長期的に見たら健全な社会です。たかが一票、されど一票。世の中そんなに無責任な人たちばかりではない。そう信じたいです。