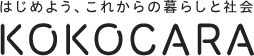ごく当たり前に「世界平和」を訴えていこう
――『虎に翼』では、戦争でさまざまな傷を負った人たちの姿が描かれています。家族を失った人や、戦後に栄養失調で亡くなった判事、路上で生きる戦争孤児など。いっぽうで、戦争そのものの描写はわずかですが、それはなぜなのでしょう。
吉田恵里香(以下、吉田) 「戦争は終結しても終わりではない」と言えばいいのでしょうか、戦争で民が負った傷を、戦後のようすを通して描きたいと思ったんです。傷を抱えながらも立ち上がらなければならなかった人々の姿や、戦後の復興の中で見て見ぬふりをしてきたことも。
例えば、戦争孤児の証言集などを読むと、「地下道で隣り合って寝ていた子が翌朝には亡くなっていた」というように、戦後も数多くの子どもたちが飢えや寒さで命を落としています。子どもの性被害も起こっていました。
私には5歳になる息子がいるので、わが子を重ねてしまいますが、たぶん誰もが「自分ごと」として想像できるのではないでしょうか。もしも戦争が起こったら、自分の大事な人が、そんなひもじくて辛い目に遭うかもしれないと。それはもしかしたら、自分の町に爆弾が落ちてくることより、リアリティーのある想像かもしれない。
いま、世の中が戦争に傾いているというか、怖い方向に進んでいる気がするので、「平和」を法律にからめてどう訴えていくか、朝ドラのチームで考えていきました。幅広い層の人たちが見る朝ドラだからこそ、「戦争を起こしてはいけない」という気持ちが高まるようなものにしたい。そんな思いがありましたね。

写真=深澤慎平
――ドラマがおおいに話題を呼ぶ中で、「平和のためにできることをしていきましょう」とSNSで発信されていましたね。戦争を起こさないために、私たち一人ひとりができることって何だと思いますか。
吉田 「戦争を起こさないようにしよう」とSNSなどで発言すると、必ず過剰に反応する人がいますよね。その人たちを気にせずに、もっとライトに……というのが正しいかわからないけれど、ごく当たり前に、まっとうに、「世界平和」を訴えていけばいいと思っています。
それで「思想が強い」などと批判してくるのは、「そのほうがよほどやばくない?」と思ってしまいます。その人たちの「結果論」や「自己責任論」でやっていくと、いずれ自分や自分の大切な人たちが、戦争に巻き込まれてしまうかもしれない。
作品についての賛否や好き嫌いは当然あっていいんですけど、「世界の平和を願う」とか「戦争を起こさないように」とか、そうした「根底の部分」に賛否が巻き起こるのは怖いなと思うんです。
まさに『虎に翼』は「思想が強い」と言われたりしましたが、じつはそんなに強いことは言っていないんですよね。「戦争反対」「男女の格差をなくそう」「どんな人も自分らしく生きられる選択肢をつくろう」など、根本のことしか言っていない。
自分としては最低限の部分にしか触れられていないと思っていたんですけれど、それさえ「ノー」と言われると、「世の中って一筋縄ではいかんわな」って気持ちになりました。学びはすごくありましたね。
余裕がなくても「きれいごと」を言っていかないと
――そういう風潮があるのは、世界各地で続いている戦争や、経済不安といった情勢が大きいのでしょうか。
吉田 それもありますし、やっぱり、誰もが余裕がないというのが大きいかもしれません。それは経済的なことだけじゃなくて、生きていると、やるべきタスクが多すぎる。すごく人間ができた人以外、99%の人にとっては、心の余裕がやさしさの核となると思うんです。

写真=深澤慎平
私は母にかなり助けられているのですが……それでも子育てって、予想していないトラブルが起こるんです。本当は、そのトラブルに備えて、自分のキャパの7、8割くらいで暮らすべきだとわかってはいるけれど、そううまくもいかない。そこにトラブルが起こると、途端にガタガタガタと崩れて、余裕がまったくなくなることが多いんですね。余裕がないと、子どもに対してもちょっとしたことで「うむむ」って怒りが込み上げたりします。
だから、「この人、感じ悪いなあ」みたいな人に出くわしたら、一瞬ムッとくるけれど、「もしかしたら、この人も余裕がないのかな」と想像するようになりましたね。
「本当に助けを必要としている弱者は、助けたくなるような姿をしていない」。これは、福祉や支援の現場でよく使われる言葉だそうです。『虎に翼』でも、その言葉を受けてつくったシーンがたくさんあります。執筆を経て、自分の余裕のない状況を重ね合わせて考えてみると、ちょっとくらい不機嫌で感じが悪い人がいても、まあいいじゃないかと思えるようになりました。
それから私のような、「余裕はないけど、それでもまだある」みたいな人が、社会の中で「きれいごと」を言っていかないといけないのかなと思います。「きれいごと」を言い換えると、「理想」とか、「当たり前のこと」とかなんですけどね。
生きているだけで、何かを脅かしている
――先ほどの話に戻すと、カギカッコつきの「思想が強い」という批判については、どう思われますか。
吉田 「何となく気に入らない」とか子どもはよく言いますけど、大人にもそうした幼い感情があって、それに理屈をつけて正論らしきものにまとめ上げている。それが「思想が強い」という批判の正体なのかもしれません。

写真=深澤慎平
「思想が強い」と言われたときに、「じゃあ、一つひとつ話し合ってみましょう」とやってみたとします。たとえば、「男女が平等で、女性にさまざまな選択肢があること」が「思想が強い」というなら、「あなたの言う『思想が強くない』というのは、どういったことなんですか?」とか。そう向き合って一つひとつ対話したとしたら、そこに明快な答えはないのかもしれない。
自分とは異なる考えや生き方を認めることについて、なんとなく押し付けられている気がして不快。そんな感情論であって、本当の理屈じゃないことが多い気がしています。
――自分とは異なる生き方を認めがたい、ということですね。吉田さんのドラマ作品には、たとえば男性同士のカップルや、アセクシュアル注釈の人、外国籍という出自をひた隠しにして生きる人など、いろんな生き方をする人が登場します。そして、その人たちの「平和」が他者によって脅かされるということが描かれていますね。
吉田 これは年齢にかかわらず……なのですが、「自分はまったく差別をしたことがないし、何かを脅かしたことなどありません」と思っている人が、どうやら本当にいるようなんです。でも、そんなはずはないというか、「それで手を挙げる人が一番やばい」と私は思っていて。
生きているだけで、自覚があるなしにかかわらず、何かを脅かしているはずなんですよね。もちろん自分も含めて。そういうことにちょっと触れて、見る人が改めて考えてくれるような作品を書きたい。「いい人」ばかり出てくる作品でも、しんどい部分も見せたい、というのはありますね。
それから、ドラマで社会問題を扱うと、ただそれだけで「メッセージが強い」とか「思想が強い」と言われる風潮も不思議です。そもそも、作品には絶対何かしらのメッセージがある。「この人が好きでたまらない」「この人のために命をかける」というドラマなら、「恋愛至上主義」というメッセージが込められていそうですが、「恋愛を押し付けるなんて思想が強いです」とは言われないわけですから(笑)。

写真=深澤慎平
ケアする人、支える人も、賞賛されるべき
――もうひとつ、『虎に翼』で印象的だったのが、「ケアをする人」のキャラクターや生きざまがきちんと描かれていたことでした。寅子の母のはる、兄の妻である花江は、専業主婦として家族を支えていきます。
吉田 はるや花江の仕事って、余裕をもって家庭を回し、家族が気持ちよく暮らしていくために重要です。寅子はそれで仕事に邁進できたのだし、私も去年はずいぶん母に助けられて『虎に翼』を書き上げ、賞をいただくこともできました。
それと同じような意味で、「賞をとった人のみならず、その人を支えていた人が、もっと評価されたり、同じくらい称賛されたりするべき」という話をSNSなどでよくするんですけど、そうすると、「全部ひとりでやってきた人はどうなんだ」とか、本質ではない部分で批判してくる人がいる。何だかムッとする人もいるようなんですよね、「何で自分のがんばりを、人とシェアしなければならんのだ」というように。
そうではなくて、何かを必死にがんばっているときは、たいていどこかに「歪み」が出ていて、それをケアしてくれている人が絶対にいる、という話です。それはパートナーや母親などにかぎらず、たとえば、駅伝のチームを支えた寮母さんなども同じ。そういう人がおろそかにされず、賞賛されるのは、本当に正しいことだと思うんです。
がんばらなくても、それなりに生きていける社会
――「それぞれが尊重し合い、心穏やかに過ごせる状態」を平和というふうに捉えたとき、そういう日常をつくるために、吉田さんが大切にされていることはありますか。
吉田 怒ることです。ダメなことにはちゃんと怒る。
たとえば、日常の中の差別的な発言などは、そこで指摘しなかったら「肯定」と捉えられてしまいがちです。「相手にしないでおこう」とシャッターを閉じるのも間違ってはいませんが、問題解決にはならないんですよね。自分はそれでよくても、シャッターを閉じる力が弱い人は苦しいんだろうなって思うんです。
正しくないことを放置してしまったら、苦しむ人がいる。それは嫌だから、なるべく見過ごさず、怒るようにしています。
――ご自分のためではないんですね。
吉田 そうですね。自分のためだったら、わざわざ怒ることはさほどないですよ。たとえば「選択的夫婦別姓」が認められない問題については、私はもともとの名前で作家活動をしているから、戸籍の名字をパートナーに合わせるのは苦痛ではありません。そしてまた異性恋愛者だから、「同性婚」が認められなくても、実生活に影響はない。
自分のことだけを言えば、どっちでもいいわけですけど、その選択肢を削られていることで、不幸な思いをしている人たち、当たり前の権利が侵されている人たちが確実にいる。それに腹が立つんです。

写真=深澤慎平
これは自分の子どもだけではなく、いまを生きる子どもたちみんなの話なのですが、みんなそれぞれに、幅広いセクシャリティーや個性の持ち主ですよね。そんな子どもたちが世に出るときに、少しでもよい社会になっていたらいい。だから、自分が正しいと思うこと、理想は言っていきたいし、怒ることが大事かなと思っています。
でも、それは「怒れる人」というか、「怒れるだけの余裕がまだある人」だけでいい。怒れない人もいると思いますから。
――そうやって、一人ひとりが生きやすい社会をつくれるといいですね。
吉田 「がんばらなくても、それなりに生きていける社会」がいいかなって、私は思っています。
人はそもそも、人生のスタートラインがいっしょともかぎらないし、個人差もあれば、育つ環境も違いますよね。がんばった人はがんばっただけ、きちんと報われてほしい。でもそのいっぽうで、がんばらなくても人にやさしくできるだけの余裕がある、とか。必死にがんばらなくても、何かを丁寧に成し遂げられた、とか。そういったことが、もっと認められてもいいような気がしています。
誰もが自分らしく生きる選択肢をもち、自分なりのがんばりで暮らせて、余裕をもって人にやさしくいられること。それが平和だと思いますし、そんな社会のために、自分がエンターテインメントの世界でできることがある。そう信じて書き続けていきたいですね。