避難者のさまざまな事情、それぞれの13年
復興庁の「全国の避難者数」によると、東北3県(岩手、宮城、福島)から山梨県内に避難した人は414人[4]。そのうち福島からの避難者が8割を超える。今回、原発事故に伴い福島から山梨に避難し、「東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会」[5]の取り組みでつながった4人のかたが取材に応じてくれた。

松本さん(写真中央)は山梨で農業を学び、農家に転身した(写真=編集部)
松本勝男さんは、浪江町の出身。勤めていた大手メーカーの工場が、南相馬市から山梨県内に移ったことから、家族全員で移住した。その後、定年退職。専門学校山梨県立農林大学校で農業を学び直し、現在は農家として暮らしている。
「震災当時、80歳だったおふくろは、住み慣れない山梨に来て、かなり参っていました。でも、山梨の人たちは親切にしてくれました。散歩中に『大変だね。うちのじゃがいも、持ってって』と声をかけてもらったりして、救われた部分もあったと思います。おふくろは福島に戻ることなく、91歳で亡くなりました」(松本さん)

塩谷さんは持ちまえのフランクさで、積極的に地元に溶け込んできた(写真=編集部)
南相馬市出身の塩谷修司さんは、妻と2人の子供(20歳、17歳)と暮らす。原発事故が起こり、「福島では子どもたちが安心して過ごせない」と考え、仕事を退職。山梨に移住し、農家に転身した。
「土に向き合っていると、一心不乱に農作業に集中できて、震災のことも忘れることができます。知らない土地で暮らす中、無尽(むじん)という昔ながらの集まりにも支えられました。仲間どうしでお金を積み立て、食事や飲み会をし、何かあったら助け合う、地域の古くからある風習です」(塩谷さん)

鍛治内さんはIT業界での経験を生かして、再就職を果たした(写真=編集部)
震災前は南相馬市で暮らしていた鍛治内永さんには、妻と3人の娘(高校2年の長女と中学2年の双子)がいる。妻と娘は先に山梨に避難し、鍛治内さんは仕事の関係で約2年、南相馬で暮らしたが、家族と山梨で暮らすことを決意し退職。現在は山梨県内で、IT関連の仕事に従事している。
「海がなく、山に囲まれた山梨の生活には、なかなか慣れませんでした。ただ、孤独や寂しさを感じたことはありません。寂しかったのは、子供たちでしょうね。福島の友達と離れ離れになり、山梨の暮らしになじむまで、時間がかかったようです」(鍛治内さん)
原発事故の避難区域に指定されなかったものの、自主的に県外避難を決めた人もいる。Aさんは、自宅のある二本松市から山梨に自主避難し、長男(高校3年)と長女(小学6年)の3人で暮らす。
「夫は今も福島にいて、山梨には毎月来てくれます。お互いの両親が高齢になったこともあり、いずれ福島に戻るつもりです。ただ、今は子どもたちのことを第一に考え、山梨で暮らしています。夫が山梨に来てくれると、家族4人で暮らせるのですが」(Aさん)
取材に応じてくれた4人にはそれぞれ、家族と日々の暮らしがある。住み慣れた福島を離れた悲しみにふける余裕はなく、目の前の生活を立て直すことで精いっぱいだった。
「東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会」の存在
4人に象徴される、おのおのがそれぞれの経緯でたどり着いた福島からの多くの避難者を、「東日本大震災・山梨県内避難者と支援者を結ぶ会」(以下、結ぶ会と表記)は常に見守り、支えてきた。結ぶ会は、行政および県内のNPO法人などで構成[6]。2011年9月から活動が始まり、県内避難者への情報提供、日常相談の対応、避難者どうしの交流機会の提供に努めてきた。

定期的に開催される交流会を通じて、避難者たちはお互いを支え合ってきた(写真提供=結ぶ会)
交流の場としては、県内11の地域で開く地域別交流サロン(2018年まで)、年に1度開催する県内避難者交流会、参加団体からの招待イベントなどがある(パルシステムが取り組む「東京電力福島第一原子力発電所事故被災者応援金」も一部活用)。中央市のレストラン「フレンチブルドック」では月に1度(原則日曜午後)、食事をしながら避難者が交流する「フレンチブルドックの会」も開かれている。
「結ぶ会は、私たち避難者のそばに、ごく自然な存在としてありました。“結ぶ会”という名前が示すように、人と人との結びつきが、とても充実しているように感じています」(松本さん)
「交流会に顔を出すと、お互いに福島弁でしゃべったり、家族といるような安心感があります。みんな同じような状況の中で頑張っていることが、交流を通じて分かってくる。結ぶ会は、山梨で生きていくための、安心して身をゆだねられる“突ったい棒”のような存在です」(塩谷さん)
県内避難者の要望や困り事を吸い上げ、国や県に伝える役割も、結ぶ会は担っている。鍛治内さんとAさんは、こんな期待を寄せる。
「私の両親も、妻の両親も、福島で暮らしています。会いに行くとき、高速道路の料金が無料[7]になるのは助かります。この制度は継続してほしいのですが、個人で国や県に陳情するのは難しい。結ぶ会には、こうした避難者のニーズを代弁してもらえるとうれしいです」(鍛治内さん)
「近い将来、長女の高校受験があります。私の本音としては、福島の高校に進学してほしい。そのためには、学校見学や受験で山梨と福島を行き来することになります。受験生への優遇措置や受験のための交通費など、支援制度ができるように結ぶ会にも協力してほしいです」(Aさん)

パルシステムは生活実態に合わせて支援物資を都度届けてきた(写真提供=結ぶ会)
原発事故への怒りにとらわれず、家族と前を向いて歩きたい
4人の胸のうちはそれぞれ異なるが、共通することもある。それは、子どもや孫の存在だ。震災から13年、子や孫の成長に、それぞれの月日と思いが宿っている。
「山梨に来て、子どもたちが福島のことを懐かしく語ることは、あまり多くはありませんでした。親の目で見ると、新たな生活の場で、本人たちなりに頑張ることで置かれた状況を受け入れてきたように感じます」(塩谷さん)
「長男は震災の後、幼いながらも本人なりに思うこと、大変なことがあったはずですが、口にはしませんでした。山梨の暮らしに慣れようと精いっぱいな私の姿を見ていたので、何も言えなかったのかもしれません」(Aさん)
「子どもは3人いますが、いちばん下の子は震災の時大学3年で、みんなもう大きかった。むしろ孫が気掛かりでした。震災当時は3歳と5歳で、福島で暮らした記憶もないまま、山梨に引っ越してきました」(松本さん)
震災後の自分の決断は正しかったのか。移住するにしろ、家族と別々に暮らすにしろ、かっとうや苦悩がある。

原発事故でかつて避難区域となった浜通り一帯には、未だ閑散とした地域も多い(写真=編集部)
「震災前に私が思い描いた人生設計が、完全に狂ってしまった。震災と原発事故がなければ、の思いは残ります。でも、怒りを抱えたところで、何か改善できるわけではありません。現実を受け入れ、自分が思い描く暮らしに少しでも近づくように努力するしかありません」(鍛治内さん)
「福島に帰るのか、帰らないのか、そのときにならないと分からない」
結ぶ会は2021年2月、震災から10年を前に、県内避難者へのアンケート調査を実施した。将来帰郷を考えている人が9%、山梨での定住を決めた人が73%、未定が18%。2割近くの人が、いまだ将来への展望を見いだせていない。
山梨で暮らすことを決めた人、ふるさとへの帰郷を模索する人、いまだに決められない人、それぞれの選択がある。子どもの進学や独立、親の介護など、家族の事情も変わっていく。話を伺った4人のうち、農家として再出発した松本さんと塩谷さんは、「今のところ福島に戻るつもりはない」と言う。
「自宅は、原発から15km範囲内にあります。2009年にリフォームしたばかりでしたが、震災後は空き巣や動物による被害がひどく、解体して更地にしました。母も山梨で亡くなり、福島に戻るつもりはありません」(松本さん)
「実家のあった浪江町では、戻ったのは1割くらいの住民です。地域のコミュニティが存続できる見通しもない中、福島に帰ることは難しいと考えています」(塩谷さん)
鍛治内さんとAさんは、子どもが独り立ちするまでは、福島に戻らないと決めている。ただ、福島で暮らす親が高齢であることもあり、「帰るのか、帰らないのか、そのときにならないと分からない」と語る。

震災後に建設された防潮堤で、浜通りの町からは海が見られなくなっている(いわき市/写真=編集部)
「私の両親は相馬市の復興住宅にいて、妻の両親は南相馬市にいます。子どもが独立したあと、お互いの両親の状況も踏まえて考えます。塩谷さんと同じく、私の地元でも震災前のコミュニティが失われました。たとえ戻ったところで、生まれ育った町の風景はもうありません」(鍛治内さん)
「親のことを考えると、いずれは福島に戻るしかないと思っています。でも、すぐには結論が出せません。夫は家族4人で福島で暮らしたいと考えていて、その話になるといつも夫婦げんかです。ですからお互い、福島の話題を何となく避けています」(Aさん)
避難者と顔を合わせ、相手の話に耳を傾けていく
避難者4人の話に、そばでじっと耳を傾ける人がいた。結ぶ会の事務局長・藤原行雄さんだ。山梨生まれで、本業のキャリアコンサルタントの経験を生かし、結ぶ会の企画・運営に当たってきた。
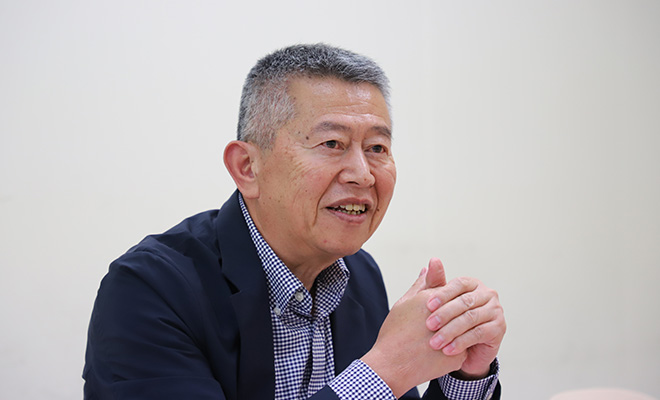
結ぶ会の事務局長・藤原さん(写真=編集部)
「一人ひとりの避難者が、どんな家族構成で、どんな困り事があるのか。結ぶ会の立ち上げと同時に、アンケート調査をしました。そのうえでそれぞれのかたと何度も顔を合わせ、相手の話に耳を傾けることに努めてきました」(藤原さん)
一口に「県内避難者」といっても、各世帯の家族構成や世代によって困り事も異なってくる。毎年開催する県内避難者交流会では、弁護士や司法書士を招いた相談ブースを設置。専門家によるサポートにも力を注いできた。
「県内に避難する当事者がどうしたいのか、そのために何ができるのか。結ぶ会では、一人ひとりの目線に立ったサポートを常に大事にしてきました。パートを掛け持ちする母子世帯のかた、独り暮らしの高齢者など、支援と見守りが必要なかたは今もいます。困ったことがあれば相談にのる関係を、これからも維持していきたい」(藤原さん)
理不尽さへの義憤と喪失感は、ずっと変わらない
結ぶ会の活動は、支援を必要とする県内避難者がだれもいなくなるまで続く。藤原さんは人生のセカンドステージを、この活動にささげてきた。その原動力は、どこにあるのだろうか。
「一言で言うと“理不尽さへの義憤”です。縁もゆかりもなく、山梨に逃げてきた人たちの姿を見たとき、そう感じました。同じ避難者なのに、賠償金をもらった人ともらえない人で分断が起きた。そうやって経済的な格差をつけた国に、疑問を覚えます。国は、福島に戻る人たちだけではなく、県外避難者への支援をもっと手厚くすべきです」(藤原さん)
藤原さんは毎年、県内各市町村の担当者を訪ね、活動報告と資料を手渡している。県内避難者の存在が、世間で忘れられないようにするためだ。「時々でいいので、ふるさとを追われた人たちのことを思い出してほしい」と藤原さんは訴える。

避難指示が解除されたエリアでも、一部はあの日から時が止まったまま(川俣町/写真=編集部)
東日本大震災のあとも、各地で天災が相次ぐ。2024年元日に起きた能登半島地震[8]では、1万人以上もの人たちが避難生活を余儀なくされている。新たな災害が起きると、それまでの災害への関心は薄れ、記憶も風化していく。しかし、当事者が受けた心の傷は、すぐにいえることはない。
「私が生まれ育ったのは、人口約2,000人の小さな町でした。同級生と先輩・後輩の家族構成、祖父母の顔まで、みんな知っています。その小さな町を津波が襲い、一度に何百もの人が亡くなりました。今なお行方不明の人もいます。その一人ひとりの顔と名前は、忘れることができません。震災で受けた喪失感は、50年たとうと100年たとうと、ずっと変わることはありません」(鍛治内さん)

更地となった跡地には、太陽光パネルで再生可能エネルギーを作り出す挑戦も見られる(富岡町/写真=編集部)




