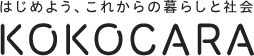暮らしもキッチンも、もっと自由に
有賀薫(以下、有賀) 駒田さんと私、同世代なんですね。食卓やキッチンに関して、思いや考え方が似ているところがあるかもしれないです。
駒田由香(以下、駒田) 有賀さんのことを書籍やテレビで以前から拝見していて、すてきなキッチンだなあと思っていました(笑)。

駒田さんのご自宅のキッチンにおじゃました有賀さん(写真=平野愛)
有賀 ご覧いただいていてうれしいです! 駒田さんは建築家というお忙しいお仕事をされながら、食事作りや子育てをされてきたんですよね。ご自身は、キッチンという場所についてどんなふうに感じていましたか。
駒田 私は大学を卒業して就職したのが、住宅設備機器メーカーのTOTOでした。「キッチン開発課」に配属され、海外のキッチンの技術を学んだり、暮らしに関する調査などをしながら仕事をしてきて、20代で独立、今の建築設計事務所を夫とやっています。
仕事を始めたころからずっと思っているのは、キッチンに限らず「あまり決めつけずに自由に」ということですね。
有賀 自由というのは、もっとその人に合ったものを、ということですか。
駒田 はい。今は、暮らし方も本当にさまざまなので。
私は母親が料理の意識が高くて、ずっと手作りの料理を食べて育ったんですよ。就職して以来ずっとフルタイムで働いていますが、ものすごく忙しいのに手作りしなきゃというのが染みついていて……。子どものお弁当なんかも手作りしていました。そういう時代だったんだなと思うんですけど。
今は、お惣菜や半調理品もいろんなものがあるし、ごはんの炊き方ひとつでも、炊飯器、お鍋、土鍋、いろいろあります。ご夫婦で住まいの相談にいらして、男性が主体でキッチンの相談をされるかたも増えてきました。

「自分が就職したころは、まだ女性総合職第1号というような時代でした」と話す駒田さん(写真=平野愛)
有賀 キッチンの使い方、ごはんの食べ方、料理をするのはだれか……。どんどん多様になっていると感じます。私も、以前は女性を「家事をやらなきゃいけない」というプレッシャーからどう解き放っていくか、ということをずっと考えてきたんですが、時代は確実に変わっていて、若いかたたちはもう、そんなプレッシャーなどなくなっています。次のフェーズを考えていかないといけないと思っているところです。
キャスター付きワゴンが「余白」を作る?
駒田 本当に時代が変わりましたよね。だからキッチンでいうと、「こうしたら使いやすい」「このレイアウトがいい」という正解はなくて、もっと一人ひとりの自由でいいと思っていて。日本は、分譲マンションやモデルハウスでも、対面式キッチン注釈がすごく多いですよね。何となく画一的で、「これがいい」という「思わされ込み」も起きてしまうなと感じています。
とはいえキッチンは、家に最初から備え付けられていることが多いので、なかなか変えようというのは難しいのですが。そんななかでも何か「余白」のようなものが作れるといいなと思っています。後からどうにでもできる部分、みたいな。

「引き出しのカトラリー入れも、自分でフレキシブルに収納場所を決めてもいいですよね」と話すお二人(写真=平野愛)
有賀 なるほど。余白とか、幅を持たせておくというのは、何事においても重要ですよね。キッチンの「余白」というのはどういうものなんでしょう。
駒田 生活って変わるものじゃないですか。引っ越しを考えたときと、実際に入居するときでは、もう変わっている。家族構成も変われば、暮らし方も考え方も変わっていくので、住まいを最初からそれに合わせるなんてできない。でも「余白」があれば調整できるのかなと。小さな棚ひとつ、引き出しひとつでもいいと思うんです。
わが家は今25年住んでいますが、独立して初めて設計したのが、自宅が入っているこの建物です。一生住むかどうかわからないなというのもありましたし、配管やダクトのあるキッチンの位置は簡単に動かせないので、全部壁際にして、真ん中にフレキシブルな空間を作り、そこに家具屋さんに作ってもらったキャスター付きのワゴンを置いています。

駒田さんのキッチンで、さまざまな用途で活躍するワゴン(写真=平野愛)
有賀 これ動かせるんですね。いいですね!
駒田 人が来るときは動かして食卓側を広くしたりして。中は引き出しと収納になっています。25年使っているのでかなり古くなっています。
有賀 うちにも夫が作ってくれたワゴンがあるんですけど、あちこち動かせていいんですよ。電子レンジやトースターを置いていて、コンセントさえあれば家じゅう動かして使えると思ったら気楽で、台所の動線が自由になったなあと。
駒田 ワゴンを買うとか、DIYで作るとかなら、そこまで大きな事じゃないですもんね。動かせるから、家族が増えたときも、建築設計事務所のスタッフと大人数で調理するときも、キッチンのスペースを広げられたんです。子どもが大きくなって、お互いいない日が増えて暮らし方が変わったら、また少し変えたり。そういう変化に、余白があったおかげで対応できたのかなと。
有賀 部屋の作りがすごくシンプルですよね。だからこそ変化が起きても使いこなせるというか。生活って大体が思うようにならないことを、実感としてお持ちだからこその発想だなあと思います。

駒田さんのご自宅は、シンプルな長方形の箱が井桁状に3層に積み重ねられている(写真=平野愛)
駒田 設計を依頼いただくお施主さんも、設計中に家族が増えることになって部屋が足りなくなったり、急な転勤だったり、予測できないことも起こります。だから、現在の生活に合わせる、未来を想定する、というよりは、状況を柔軟に取り込めたり、変化を許容できる空間づくりが大事なんじゃないかと思っています。
キッチンは「料理する場所」じゃないときがあってもいい
有賀 私の実家のキッチンも、リビングに壁付けになっていて、仕切りもなく完全にフルオープンの作りでした。なので母が料理をしている後ろ姿が、リビングにいる家族にはずっと見えていて、いつごはんが始まるかも呼ばれなくてもわかるという。
そんな家で育ったので、奥まったキッチンでだれか一人が作っていて、「ごはんだよ」と呼んで初めて家族が来る、というのにすごく違和感があって。キッチンをもっとオープンな場所にしたくて、家の備え付けのキッチンとは別に作ったのが「ミングル」注釈なんです。

IHコンロ、シンク、作業台がコンパクトにまとまった、有賀さんのご自宅の「ミングル」(写真提供=有賀薫さん)
駒田 IHコンロがビルトインされているんですね。日本の家庭料理は鍋も焼き肉もしますし。
有賀 みんなが囲炉裏みたいだねって言うんですけど、まさにそういう感じ。夫とは最初、キャンプのときの「頼んでもいないのにみんながやりたがる感」を家の中に作り出せるといいよねって話していました。
キッチンが孤独な場所にならず、だれかが料理をしている間も、みんなとコミュニケーションが持てる場所にしたかった。夫は全然料理をしない人だったんですが、何かしらキッチン周りをうろうろするという状況が生まれています。
駒田 先ほどのワゴンの話のように、ミングルも使う人や時間によって変化させられる、というのがいいですよね。人が集まってコミュニケーションの場になるだけではなく、一人用のミニマルなキッチンにもなる。
キッチンの役割って、なかなかひとつの機能におさまらない。多様で、大きな可能性を秘めていると思っています。

「キッチンが変わると、暮らす人にも自然と変化がある」と有賀さん(写真=平野愛)
有賀 ミニマルにしたいというのも最初に考えていたことなんです。一人暮らし向けの賃貸住宅のキッチンってあまりに寂しいところが多くないですか。
だったら部屋にミングルを置けば、ごはんを作る場所にも食べる場所にもなる。片付けたら勉強や仕事もできて、人を呼べばわいわいできる。わが家のようなファミリー世帯だけではなく、一人暮らしの賃貸住宅などにもいいんじゃないかと思っているんです。
自分がわくわくするのはどんなキッチン?
駒田 私は集合住宅を設計させていただく機会も多いのですが、例えば20平米台の小さなワンルームって、画一的な間取りがよく見られます。細長くて、ミニキッチンが廊下のわきにあって、リビングとユニットバスがあるという。
それで、玄関を入ったところに、こんなテーブルみたいなキッチンをぽんと置いて、玄関でもありキッチンでもあり、人が集まったりもできるというワンルームを設計しました。27平米の部屋ですが、暮らしがちょっと変わりませんか。平日に帰りが遅くなって、今日はごはんを作りませんというときも、ちょっとここでビールとかお茶を飲んだり、週末には友人を招いたりね。

駒田さんが設計した集合住宅のミニマルなカウンター型キッチン(写真=傍島利浩)
有賀 ミングルだ! まさに私がやりたかったことです。こういう間取りを見るだけでうれしくなりますし夢がふくらみます。
私も仕事柄、外にキッチンを借りようかと考えたことがあり、たくさん間取りを見たのですが、予算内でこれ!というのがひとつもなくて絶望してしまって。こういうものがあると知ったら、これから先にもっとこういうキッチンが増えるかもしれないと希望が持てます。
駒田 建築って、新しい生活の提案をすることだと思っているんですよね。だれかのために、想像しなかったような新しい日常を作っていきたい。
有賀 私もまったくいっしょです。だれかの暮らしのなかに、新しい発想や価値観が生まれてくれたら楽しいなあと。
そうそう、ミングルをSNSで見て、ご自分で簡易的なものを作った、とおっしゃってくださったかたがいたんですよ。水回りはさすがに大掛かりなので、台とIHコンロで。
駒田 IHならコンセントがあればできますからね。そうやって、自分自身で考え方を柔軟にしていこう、ということですよね。

「住まいのことも料理も、無意識に『そういうものだと思っていた』ということが多いですよね」と駒田さん(写真=平野愛)
有賀 そうです、そうです。「自分のキッチンをこうしたい」と考えるきっかけになれたことがうれしくて。住宅のことってどうしても、あるものを選ぶというか、受け身にならざるをえない部分もありますし。
料理も同じなんですが、みんな「やらされすぎている」んです。自分の暮らしのことや自分が食べるものを、自分で決めていいんだと思えなさすぎている。レシピもひとつのマニュアルのようなものですが、「従うべきもの」と思い込んでしまうんですよね。本当は、正しいものは自分の内側にあるのに。
今抱えている料理や暮らしに対するモヤモヤを解消するには、そこをどうやってマインドチェンジするか、だと思っています。
「曖昧な場所」にこそ人が集まってくる
駒田 私たちの事務所があるのが「西葛西APARTMENTS-2」という建物なのですが、事務所とコワーキングスペースがある2階のエントランスを入ってすぐのところに、横幅3mの大きいキッチンをあえて置いたんですよ。

西葛西駅から徒歩10分ほどの場所にある、「西葛西APARTMENTS-2」(写真=平野愛)

2階の入り口を入ってすぐのところにあるキッチン。奥がコワーキングスペースになっている(写真=平野愛)
有賀 ドアを開けたら本当にすぐありますね。奥にあるイメージのキッチンが、ぽっと飛び出してきている。
駒田 事務所のスタッフも、コワーキングスペースの利用者も、ここで飲み物を入れたり、お弁当を温めたり、コップを洗ったりするので、「とどまる場所」になる。キッチンに用事がなくてもここを通らないと出入りできないから、自然なコミュニケーションが生まれるんですよ。ちょっと立ち話をしたり、「いってらっしゃい」と声をかけたり。
有賀 ミングルの役割とも非常に似ていますね。キッチンという場所ではあるけれども、入り口でもあり、通路でもあり、ちょっと人がたまる場所でもあり、いろいろな目的が混ざった場所。
駒田 そうなんです。「曖昧な場所」って、人と人がゆるやかに交わる場所でもありますよね。1階のデッキ部分もあえて動線が交わるように設計していて。
有賀 1階のパン屋さん、常にお客さんがいらしていて、カフェやテラス席もにぎやか。住宅街の真ん中とは思えないです。

取材中も、パンを買う人、上階から下りてきた人、常に人が行き交っていた建物わきの通路(写真=平野愛)
駒田 ここができたのが2018年になります。設計中に考えていたのは、公園以外で子ども連れで気兼ねなく行ける場所が少ないなとか、行くとしたらショッピングセンターかフードコートで、どこに行ってもチェーン店ばかりだとつまらないなあと……。
有賀 いや~。わかります。
駒田 それと、自分が建築現場からの帰りにカフェに寄ってその日の仕事を終わらせてから帰宅する、みたいなことをやっていたので、いわゆるサードプレイス的な場所があったらいいなと思っていて。
もちろん作るからには収支が回る必要があり、それなら「街が豊かになるにぎわいを作れないか」と。それで、小さな建物の中に「住まう」だけじゃなく「商う」や「働く」、「集まる」といろんな用途を詰め込もうと考えたんです。
有賀 サードプレイスという言葉自体は以前からありましたが、コロナでリモートワークやコワーキングスペースといったものが一気に進みましたものね。

午前中からいい香りが漂い、つい入りたくなるパン屋さん「ゴンノベーカリーマーケット」(写真=平野愛)
駒田 1階はカフェでもなくレストランでもなく、パン屋さんに入ってほしかったので、自分で葛西にあったパン屋さんに声をかけて誘致しました。パンだったら200円持ってくれば、小学生も一人で来て買えますしね。上の階は住居になっていて、すぐ隣にはちょっとしたイベントに使ってもらえる「やどり木」というコミュニティスペースも作りました。
そんな、さまざまな目的で来る人たちの動線を、2つの建物の間の路地のようなスペースで交錯させて「曖昧な場所」にしたんです。パン屋さんへは、前面道路からではなく、「7丁目PLACE」と名付けた路地のようなスペースから、あえて入るようにしています。
有賀 さっきそこにベンチがあって、着いてすぐについ座ってしまいました。家を一歩出たら、子どもなら道端の縁石とかでも座れるけれど、大人になるとちょっとできないから(笑)、「大人の縁石」みたいな場所があるというのはうれしいですね。

端に造りがちなスロープを、親しみのある形であえて真ん中に。ベビーカーも車いすも気負わずに通れる(写真=平野愛)
駒田 そうそう。お金を払わなくても出入りができるスペースなので、子どもがただワーッと来て帰ったり、おじいちゃんとお孫さんがセミ捕りに来たり。いろんな人がいて自由に立ち寄れる雰囲気にどんどんなっていくんですよね。
土日はお父さんと子どもが、お母さんが家でゆっくりしている間にパンを食べに来たりとか。それはコンビニで買うのとはちょっと違う体験なんじゃないかなと思います。味だけでなく、この空間に来て、何となく顔見知りの人がいて、あいさつをしたりするというのが。
有賀 何もないけどフラッと入ってしまう雰囲気ですよね。とくに都市部だと、街の中にそういう場所ってなかなかないと思います。入っちゃだめかなと思ってしまう場所が多いというか。
キッチンも地域も、もっと人が集う場所に
駒田 先日いらしていたご夫婦が「この辺、この建物ができて変わったんだよね」と話していて、自分の住んでいる地域を誇りに思ってくれていることがうれしいなと感じました。
道のわきに石を置いているんですが、たまに子どもが遊んでいてつい投げちゃうこともあります。でも、そういうことが起こるたびにルールを作って厳しくしていくと、「場所」って退化していくんじゃないかと思うんです。
みんなが見守っているからだれかに迷惑をかける行動はしないとか、ふだんからきれいになっているとポイ捨てしようなんて思わないよねとか、いい雰囲気をみんなで醸成していくというか、地域ってそういうふうであってほしいと思います。
そして何よりも、コミュニケーションがとれる顔見知りの人が地域に増えいくということは、暮らしに安心が生まれますよね。

「西葛西APARTMENTS-2」を訪れると、自分と地域のつながりをふと考えるきっかけにも(写真=平野愛)
有賀 地域のかたにとって、おいしいパンを買って憩うだけじゃなく、コミュニケーションのきっかけを作る場所になっているのがすてきです。
私は料理家なので、よく箱ごと食材が届いたりするのですが、同じマンションの住民のかたに声をかけておすそ分けをしています。ちょっとした雑談をするだけで違うものですよね。それに、子どもをみんなで見守るというか、身近に安心できる大人を増やしていくことは、地域を気持ちのよい場所にするために必要なことだなと。
駒田 私自身も、地域のかたにあいさつをすることが増えました。無理せず自然体で、ゆるやかなつながりが広がっていけば、街も、自分自身の暮らしも変わっていくのではないでしょうか。
有賀 人間関係ってどうしても多少煩わしいもの、面倒が含まれるものですが(笑)、人と人が暮らしの中で交わる場を大切にしたいなと改めて思いました。キッチンも家も街も、「余白」と「曖昧さ」でコミュニケーションや自由な発想が生まれるんですね。

写真=平野愛