「みそ汁飲め!」から、発酵にはまった
――小倉さんといえば、2011年に老舗みそ屋「五味醤油」さんと作った「手前みその歌」がヒットして全国に広がりました。そのあとに出された著書『発酵文化人類学』(角川文庫)も話題になり、最近では東京・下北沢に各地の発酵食品を扱うお店「発酵デパートメント」もオープンされています。お店には若い世代のお客さんも多くいらっしゃるそうですね。
小倉ヒラク(以下、小倉) 下北沢という場所もあって、発酵デパートメントには20代から30代くらいの若いお客さんやクリエイターの人たちも多いんです。
お店では全国各地で見つけてきた発酵食品やオリジナル商品を販売しているんですが、「実はこんなものを作っているんですけど……」という思いがけない商品の売り込みも全国から来る。だから最初は自然食品店みたいな品ぞろえだったんだけど、今はだんだんマニアックなラインナップになってます(笑)。

各地の発酵食品がずらりと並ぶ発酵デパートメントの店内(写真提供=小倉ヒラクさん)
――発酵に興味を持ったきっかけは何だったのですか?
小倉 以前、スキンケアの会社でデザイナーをしていたのですが、そのときの同僚が五味醤油の娘さんだったんですよ。
当時、僕は夜遅くまで働き、朝まで友達と遊ぶ生活を繰り返して体調を崩していました。そんなときに、その同僚と一緒に、発酵学者の小泉武夫先生に会う機会があったんです。
小泉先生は僕の顔を見るなり、「お前、免疫不全だな。みそ汁飲め! 納豆と漬物食え!」と。それを実行してみたら本当に体調がよくなったので、「発酵って面白いな」と思うようになりました。それまでは食そのものに全然興味がなかった。

写真=豊島正直
――それは意外です。小倉さんは「発酵デザイナー」という、ちょっと珍しい肩書をお持ちですね。
小倉 その同僚からみそ屋のデザインを頼まれたのを皮切りに、酒蔵やしょうゆ蔵、ビールメーカーなどから仕事を依頼されるようになり、気づいたら発酵に関わるデザインが増えていました。それで「発酵デザイナー」と名乗るようになったんです。
そこから、もう少しちゃんと勉強しようと思って東京農業大学醸造科学科の研究生になって、微生物の世界について本格的に学びました。
人間に役立てば「発酵」、有害なら「腐敗」
――みそやしょうゆや納豆など、発酵食と呼ばれるものはいろいろありますが、「発酵」とはそもそも何なのですか?
小倉 「発酵」とは、基本的には人間に役に立つ微生物の働きのこと。反対に、人間にとって有害な微生物が働くと「腐敗」です。例えば、みそは煮た大豆に良い菌が入ってできたものです。もし悪い菌が入れば大豆はデロッと溶けてしまって、食べればおなかを壊します。
大豆には微生物が好きな栄養素が多いので何かしら菌がくっついちゃうのですが、良い菌がくっつけば腐らずに保存ができるし、しかも、おいしくなる。「じゃあ、 なるべく良い菌がくっつくように環境を整えましょうよ」というのが発酵食の始まりなんです。
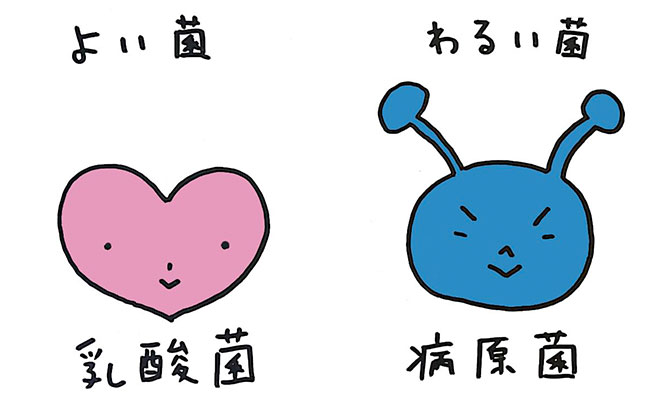
イラスト=小倉ヒラクさん
――発酵も腐敗も微生物の働きという意味では同じなのですね。昔ながらのみその作り方にも、良い菌がつきやすいような工夫があるということですか?
小倉 大豆をつぶすのは菌がつきやすくするためですし、塩を入れるのは悪い菌が生えないようにするため。つぶした大豆を容器に入れるときに空気を追い出すのは、空気を好む菌が入ってしまうと、みその発酵が邪魔されてしまうからです。
みそ作りの工程の一つ一つに、ちゃんと意味があるんですよね。昔から伝わってきたみその作り方には、良い菌だけが働くように誘導するための理にかなった工夫が詰まっているんです。そこがすごいところ。

つぶした大豆、塩、こうじを混ぜ、空気を抜きながら容器に詰める(写真=編集部)
目に見えない微生物の力で想定外の味に
――小倉さんにとって、発酵の魅力とは?
小倉 目には見えない微生物の力が働いて、全く予想がつかないものが出来上がったり、自分では作り出そうと思わない想定外の味がバンバン出てくるのが楽しい。そういうところが、やっぱり僕は好きですね。

写真=豊島正直
料理をするのと発酵食を仕込むのってけっこう違っていて、料理の場合はイメージしたおいしい味をオペレーションに沿って作っていく感じですけど、発酵食は、しばらく放っておくと微生物が働いて、最初と全然違うテクスチャーになっちゃう。自分で「こういうふうに作ろう」と思ったわけじゃないものができるんですよね。
何百年と続いている酒蔵でも、やっぱり味は揺れるんですよ。それをどう調整していくのかがプロの発酵技術。最近では、気候変動の影響があってどこも揺れに悩んでいます。
みそを毎日食べても飽きない理由とは?
――みそやしょうゆなど日々の食卓に発酵食は欠かせません。でも、どうして私たちは、みそを毎日食べていても飽きないのでしょうか?
小倉 「煮た大豆を毎日食べなさい」と言われたら、たぶん途中でちょっと飽きますよね。でも、みそなら毎日食べても飽きない。それは、発酵によって栄養分が細かく分解されているから。

写真=編集部
どういうことかというと、大豆にはたんぱく質が多く含まれていて、みその発酵過程でそのたんぱく質の一部がアミノ酸に分解されるんです。このアミノ酸は細胞の材料になるので、人間の体にとって必要度が高い。人間って「これはすぐに自分の体の材料になりそうだな!」というものを食べたときに、「おいしい」というフィードバックを受け取るんですよ。
ふだん、僕らは何かを食べたあと、腸の中で食べ物の分子を小さくして体の材料として取り込みやすくするのですが、発酵食はその作業を菌がすでにやってくれているというわけです。
――なるほど、体の材料として必要なものだから飽きないし、おいしいと感じやすいんですね。
小倉 ただし、だれにとっても分かりやすいおいしさもあれば、何だかちょっと微妙なやつもある(笑)。たとえば、苦みや酸味、渋み、えぐみ、辛みといった要素が増えると、それを「おいしい」と感じるかどうかには文化差や好みが影響してきます。
みそでいうと、愛知県岡崎市八丁町で作られる豆みその「八丁味噌」は、渋みやえぐみ、酸味などが強く、ほかの地域の人が食べると「何じゃこりゃ!?」ってなる。九州のみそはあまり熟成させず、麦を主体にした甘口で癖のない味だからだれでも食べやすいけど、ふだんそうしたみそを食べている人が「八丁味噌」のみそ汁を飲むとびっくりするんです。

独特の酸味と、濃いうまみが特徴の八丁味噌(写真=編集部)
日本は、カビを使いこなす技術がスゴイ
――小倉さんは国内外の発酵食を訪ね歩いていますが、日本の発酵食の特徴は何でしょうか?
小倉 うーん、そうですね。「いろいろな種類がある」ということが、まず特徴じゃないでしょうか。
そもそも東アジア自体が豊かな発酵文化を持つ地域で、中国、韓国、日本は発酵食のバリエーションが非常に多いんです。理由としては、食材の種類が豊富で、湿度が高く、四季があること。冬を越すために保存食が必要で、夏は暑くて食品が腐りやすかったことなどが考えられます。
その中でも、カビを使った発酵文化の洗練度でいえば、日本がいちばん高い。発酵技術の洗練度においては比肩する国がないくらい、かなり特異な発達をしてきたのが日本です。
――「洗練度」というのは?
小倉 日本では、日本酒を作るときに麹室(こうじむろ)というカビ専用の部屋を用意しますよね。温度と湿度の調整も細かく体系化されています。ほかの国を調査しても、そういう例はあまりない。中国の紹興酒も作り方は似ていますが、麹の発酵は半屋外で行いますし、もっとおおらか。カビを使いこなす技術という意味では、日本はトップレベルだと思います。

湿度と温度が管理された麹室のようす(写真提供=丸久味噌株式会社)
どうしてそうなったかというと、日本はコウジカビ(麹菌)文化だということがあります。コウジカビはほかの菌に負けやすくて雑菌が入りやすい。だから手順をきちんと踏まないとうまく発酵しません。中国をはじめとする大陸はクモノスカビ文化で、コウジカビよりも雑菌に対して強いんです。
江戸時代に花開いた発酵文化
――雑菌に弱いからこそカビを使いこなす技術が洗練されていき、今のようなしょうゆやみその作り方が全国に広がっていったのでしょうか?
小倉 しょうゆやみそに関していえば、そうした側面もあります。
主要な発酵技術が形成されて、発酵文化が花開いていくのは江戸時代ですが、日本では室町時代後期から江戸時代にかけて産業が大規模化して、マスプロダクト化していくようになっていきます。それができたのは、戦乱の時代がいったん終わって社会が落ち着き、資本蓄積ができるようになってきたから。
ただ、今でも全国には、非常にローカリティのある、その土地ならではの個性的な作り方や味の発酵食がたくさん残っています。
――産業が大規模化されていく中で、何もかもが均一化されたわけではないのですね。
小倉 その時代は藩単位ですからね。エリアごとの地域性というのがやっぱり強いので。
その土地ならではのユニークな味
――小倉さんが日本各地で出会ってきた発酵食の中で、とくに「ユニークだな」と感じたものはありますか?
小倉 いろいろありますが、石川県白山市美川に「ふぐの卵巣ぬか漬け」というのがあります。ふぐの内臓には猛毒がありますが、その卵巣を解毒して作った発酵食です。2年以上かけて熟成・発酵させた珍味で、酒の肴やお茶漬けにしてもいい。めっちゃおいしくて僕は好きです。

猛毒のあるふぐの卵巣も、時間をかけて発酵させることで最高の珍味に (写真提供=小倉ヒラクさん)
――そこまでして猛毒のふぐの内臓を食べるところが、何だかすごいです……。
小倉 実は、これは江戸時代に加賀藩の戦略によって生み出された商品なんです。地域の特産品で儲けるために、加賀藩が「こういうのを作れ」と指令して作らせたのが始まりで、今でいう“地域ブランディング”ですね。
すごく今っぽい感じですが、それが江戸時代には行われていました。
――ほかにも、そういった地域の特産品として作られた発酵食の例はあるのでしょうか?
小倉 伊豆諸島・新島の「くさや」もそうです。くさや液に魚を漬けて発酵させ、天日で干して作ります。くさやが生まれたのは江戸時代中期あたり。新島は塩の租税地で、塩を幕府に取り上げられてしまうので、魚を塩蔵するときに漬け汁を使い回すようになった。そこから多種多様な菌で複雑に醸されたくさやが誕生しました。
それを島外の、今でいうインフルエンサーみたいな人たちが「これは面白い!」と言い始めたことで広まり始めて、島ぐるみで販売用のくさやをたくさん作るようになったんです。そのときは海岸がめっちゃ臭かったという話が資料にも残っています。
閉鎖的な場所のほうが個性的な発酵食が生まれやすいので、島や山中の村、アクセスの悪い港などに行くと、面白い発酵食にいっぱい出会えます。

新島では200年以上継ぎ足されてきた漬け汁「くさや液」が今も使われている (写真提供=小倉ヒラクさん)
発酵と腐敗は、実はあいまい!?
――そうした発酵食の中には、素直に「おいしい」とは感じにくいものもありますよね。それは慣れの問題なのでしょうか?
小倉 基本的には慣れですね。先ほども言ったように、味に複雑な要素が増えるほど文化差や好みの問題が出てきます。
――海外などで自分が知らない発酵食を食べると、これは発酵しているのか腐っているか……と強烈な味やにおいに驚くこともあります。
小倉 ありますよね。人間にとって良ければ発酵、悪ければ腐敗というのが定義ですが、その線引きは、実際には文化によってあいまいです。
好き嫌いもありますしね。みんなが「これはおいしい」というコンセンサスを作ることで、おいしいという文化的な価値が生まれる。文化にはそういうイリュージョンみたいな部分もあるんですよ。
昔ながらの作り方がいちばん合理的
――十数年前に小倉さんが「みそ作りワークショップ」を開いたときは、周りにみそを手作りしている人は少なかったそうですが、最近ではみそ作り教室があったり、手作りキットが売られていたり、みそや甘酒などの発酵食を自分で作る人も増えました。一方、「みそを作ってはみたもののカビさせてしまった」という声も聞きます。
小倉 発酵食を初めて作るなら、塩こうじや甘酒がおすすめです。この2つには発酵の基本が詰まっていますし、みそより短時間でできて、まず失敗しません。
みそ作りに関して僕に言えるのは、「アレンジするな」ということだけですね。昔ながらのみその作り方がいちばん合理的にできているので、基本通りに作ればほとんど失敗はしません。
最近、時短で作る発酵食レシピなども出てきていますが、基本をアレンジしたり手順を省略したりするには、発酵の原理をきちんと理解していることが必要です。そんな知識がなくても、みんなが失敗なく作れるのが、昔から伝わる作り方なのです。

「初めての発酵食作りには、塩こうじや甘酒がおすすめです。ヨーグルトメーカーや炊飯器を使えば温度管理も簡単。うちでは泡盛に使う黒こうじで甘酒を作っています」と小倉さん(写真=豊島正直)
――「基本のレシピ」をしっかり守ることが失敗しない道なのですね。
小倉 みそ作りでやりがちな失敗の原因の一つに、塩をケチってしまうことがあります。減塩ブームでも絶対に塩はケチってはいけません。
塩を減らすと腐りやすくなるので、失敗したら目も当てられない。カビを心配する人も多いですが、多少生えても問題はありません。表面に塩をまぶすのは、カビが生えてもそれ以上中に入ってこないようにするためなのです。

米こうじと塩を入れ、両手をすり合わせるようにしてよく混ぜる(写真=編集部)
表面にきちんと塩をまぶし、ラップなどをかけて重石をする。そうすれば、ほぼカビは出ない。それでも端っこにちょっとカビが出たときはスプーンで取ればいいだけです。
先人が失敗を重ねて練り上げてきた作り方なので、まずはそのやり方を信じましょう!
みそ作りは「コミュニティ活動」
――若い人も含め、みそを手作りすることに関心を持つ人が増えてきているのはどうしてだと思いますか?
小倉 昔はみんな必要にかられてみそ作りをしていた部分がありますけど、今はスーパーに行けばおいしいみそが買えるので、手作りすること自体に合理的な理由はないんですよね。
それでもこれだけ広まったのは、みそ作りが基本的に「コミュニティ活動」だからだと思うんです。みそって大勢で集まって一気に作ったほうが楽なので、友達や家族と一緒に作るという人が多い。みそを作ると周りの人に配ったりもしますよね。そうしたコミュニティ活動の部分に魅力や面白さを感じる人がたくさんいるんだと思います。

イラスト=小倉ヒラクさん
それに、自分が作ったみそってけっこうワイルドな味がするんですよね。
――ワイルドな味?
小倉 販売されているみそは、だれもがおいしいと思えるように味のバランスが整っている。でも自分で作るとそうはいかない。おかしなバランスになるときもあります。それでも、みそにはうまみがいっぱいあるし、塩分も入っているから、まずくは感じないですよね。かえって、そういう予想のできない味が、新鮮に感じられたりもする。
大手メーカーのビールって味がもう完成されていますけど、個性的なクラフトビールを飲むのも楽しいじゃないですか。それと同じことを手作りみそに感じている人も多い気がします。均一な味ばかりじゃなくて、多様な味を楽しめる文化のほうが面白いし、豊かだなと思います。
発酵食は手抜きをするための技術
――微生物という自然の力にゆだねる余地が大きいところが発酵食の面白さでもありますね。ただ、時間が必要なものも多いので、それを手作りする際のハードルに感じる人もいるかもしれません。
小倉 でも、本質的には発酵食を作るのって、料理の手抜きをするための技術なんですよ。例えばヨーロッパで本格的なスープを作ろうと思うと大変です。香草を束ねたり、肉を何時間も煮込んだり、野菜をくたくたに煮てブレンダーにかけたり……いろいろと手間も時間もかかるじゃないですか。かなりめんどくさい。
それに比べたら、みそ汁はめちゃくちゃ簡単。ちゃんとしたみそがあれば、出汁をとらなくても豆腐やわかめを加えるだけでおいしい。それは微生物がすでに時間をかけておいしくしてくれているから。その微生物の恩恵にあずかるのが発酵食の神髄で、結果として人間は料理の手間を省けるのです。
発酵文化の10年、20年先を見据えて
――小倉さんは、今後どんなご活動をされていく予定でしょうか?
小倉 今は店舗の運営がメインで、そのほかにも発酵に関する展覧会やツアープログラムのプロデュース、研究開発といった活動もしています。
日本の発酵食は世界の食の大きなトレンドになっていて、ミシュランガイドで星がつくような海外のレストランから「日本の発酵食についてレクチャーしてほしい」という依頼が多くあります。日本でも発酵食ブームが広がって、ここ十数年の間に発酵食の認知度はかなり高まりました。
その一方で、発酵食を支えてきた地方で進む高齢・過疎化や、今の流通の仕組みでは作り手側にあまり利益が行かないといった構造的な問題など、課題もたくさんある。僕自身は、これから10年、20年先を見据えて、発酵に関わる産業や文化が長く継続できる仕組み作りにもっと取り組んでいきたいと思っています。

写真=豊島正直
――発酵文化を未来につなぐための活動に力を入れていかれるのですね。
小倉 発酵文化には、各地域の大事なものをたくさん守ってきた側面があります。今僕が住んでいる山梨からワイン文化がなくなったら、ぶどう畑の景観もなくなってしまう。日本酒の酒蔵がなくなったら、周辺の田んぼも減ってしまいます。
農家さんの暮らし、地域のお祭り、 その土地の産業基盤など、発酵文化が守ってきたものは大きい。そうしたものが失われないように取り組むことは、自分の仕事として最低限の責任だと感じています。
それに、世界じゅうどこも均一なおいしさばかりを求めて、「気づいたら町じゅうがチェーン店」みたいになったら面白くないじゃないですか。発酵食はまったく予想もつかない味を生み出すからこそ、国内外に多様な味の文化も生まれてきた。そこに魅力を感じているんです。




