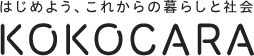好きなことを楽しく。幸せの総量が増える場所を作りたい
――桑田さんご自身も、福祉関係の仕事をされていたのですよね。「スタジオてくてく」(以下、てくてく)を立ち上げるに至った思いを教えてください。
桑田浩明(以下、桑田) 3年間ぐらい障がい福祉の仕事をしていました。就労移行支援注釈、就労継続支援B型(以下、B型)注釈、児童発達支援……。現場スタッフ、管理者、事業部長、人事、役員と、いろいろな状況や立場を経験しました。
でも一言でいうと、「つまらない」と感じてしまったんです。
それまで学校や企業になじめなかった方が「一休み」するために福祉事業所に来ている、というケースもあるはずなのに、一律に「無理に既存の仕組みになじませようとしている」ようにも感じてしまって。
「福祉サービス」というのは行政サービスの一環なので、厚生労働省、自治体が決めたルールの中で何かサービスを提供する、という主旨はわかります。でも、仕組みの部品として人が扱われてはいないだろうか、という違和感もぬぐえなくて。
そこで、利用者の皆さんといろいろ話してみたんです。すると、アニメ、漫画、YouTubeなどが大好きなかたが多くいて、その話をするときは目を輝かせているなと。
僕もアニメとか漫画がすごく好き。そんな好きなことに接点を持った仕事なら彼らも楽しめるんじゃないかと、B型事業所とサブカルチャー(以下、サブカル)のクリエイティブを掛け算する場所を作りました。

写真=写真工房坂本
――利用者さんにとってだけでなく、スタッフの立場としても画期的な場所ですよね。
桑田 福祉業界で働く人は本当に尊い仕事をしているんですよね。利用者さんのためなら行政サービスの枠を越えたことでもやろうとするし、そこにちゃんと誇りを持っている。だけど、給料は安いし下手をすれば「やりがいの搾取」もあって、人がどんどん辞めていく。
本来仕事は、やりがいや誇りを感じながら楽しく頑張るもの。相手から「ありがとう」という言葉がもらえたら、そこに幸福が生まれる。その循環を作り出して社会の幸せの総量を増やすために仕事はあるのだと思うんです。だから、働く人にとっても生き生きできる職場を作りたいなと考えながら、この事業所をやっています。
医師もびっくり! あふれ出る生命力とみるみる伸びるスキル
――利用者さんはどんなきっかけで「てくてく」に通われるようになるのですか?
桑田 利用者さんのうち大体5~6割ぐらいは福祉サービスを初めて使うかたなんですよね。
福祉事業所だからではなく、てくてくでは自分の好きなことができると感じて来ていただけるかたが多いというのは特徴的だと思っています。家で引きこもりがちだった方が自分でWeb広告を見つけて来るほか、行政、学校の先生、お医者さんなど周囲からの口コミで半数ぐらいは紹介いただけるようになりました。
そのうち約8割は「働くこともあきらめていた」というかたですが、彼らを見ていると、やっぱり今の社会で生きていくのはしんどいだろうなと感じます。疲れやすいし、ちょっとしたことですぐにへこむし。自分がそもそも働けるとは思っていない。
何か世の中、「無理ゲー」注釈感と言いますか……そんなふうに感じているかたが多い印象はあります。

写真=写真工房坂本
――そこから踏み出す一歩は、大きなものですね。
桑田 皆さんそれまで長く引きこもっていて体力もないので、初めは通えても週1日、2日とか。例えばアニメの仕上げ作業なら、機密情報でもあるので事業所でしかできません。すると徐々に、週3日、4日、5日と通い始めるんですよ。
もうお医者さんとか親御さんがびっくりしちゃって。「何かしたんですか!?」と聞かれても、僕らは特別なことは何もしていない。アニメの仕事がしたいからから本人が勝手に来ちゃうんです。結果、週5日通うと体力もつくし、生活リズムも整うし、おなかがすいてご飯も食べるし、太陽の光を浴びれば自律神経も整ってきてどんどん調子がよくなる。
目標として先に決めてしまうのではなく、自分が心から選んだことをやるという目的があれば、意志を持って家を出る習慣ができる。その環境があることがいちばん重要で、僕らが変えるというより彼ら自身がもともと持っているものが自然とあふれ出たという感じですかね。
――好きなことをやり始めたら、そんな好循環が。きっと没頭してしまうのでしょうね。
桑田 特に若手では、技術の習得がとにかく速いかたもいて。例えば2Dイラストに立体的な動きをつけられるLive2Dというソフトウェアでは、半年ぐらいでプロレベルまで一気に駆け上がって、今は商業レベルの案件をどんどんこなしているかたもいます。
やっぱり好きなことをやり続けると、こんなに人って成長もするし、体力もついてくるし、安定して働けるのだなと。頼もしさを感じます。

利用者Hさん(20代)はもともとイラストを描くことが好きでLive2Dに興味を持ち、「てくてく」に通い始めた。「創作に対する姿勢が似ている人やさまざまなスキルを持った人たちに囲まれて話ができる環境が新鮮。今、頑張って習得しているスキルをさらに究めて、要望や予算に合わせながら自分にしかできない表現ができるようになりたい」(写真=写真工房坂本)
さらに最近の例でいうと、とあるWebアニメ制作のお手伝いを大々的に受注しているのですが、アニメってただ絵を描くだけじゃなくて、文脈、ストーリーの背景を踏まえてキャラクターの表情を作る必要があるんですね。その理解度が非常に高いとクライアントから評価していただける利用者さんがたくさんいます。
「障がい福祉だから発注する」ではなく、数限りないクリエイターの中から選ばれて、「てくてくの○○さん、□□さんとぜひお仕事をしたい」と指名頂けることも。これは本当にぐっとくるというか……。そうだよね、やっぱり障がいのあるなしにかかわらず活躍できる分野はあるんだよね、と深く実感します。
――クリエイティブ業界としても、才能の原石発掘につながっているということですよね。
桑田 雇用という観点では、1日8時間・週40時間働けるということが前提になりますが、例えば夜だけとか、1日4時間とか、2日間働いて1日休むとか、各々のリズムであれば素晴らしい作品を手掛けられるクリエイターが、現状では除外されてしまっていますね。

Sさん(20代)は、2年半ほど前からてくてくに利用者として通い始め、指名で仕事の依頼が来るほどのスキルの高さから、クリエイタースタッフとして、てくてくに就職。もともと好きだったイラストやLive2D関連の制作だけでなく、事業所内のツール練習用デモデータの制作にも取り組む。「スタッフの側で働くようになり、みんなが作業しやすいように裏でさまざまな環境を管理する一員になれたのがうれしい。これからはビジネスマナーなども学んでいきたい」(写真=写真工房坂本)
その人の人生。ありのままに寄り添い、見守る
――皆さん一様に、やりがいと向上心を持ってスキルアップを目指されるのでしょうか?
桑田 初めはもちろん一人一人の力量が読み切れません。現実的に、商業レベルでのクリエイティブの受託案件をきちんと担えるスキルがある人は全体の2割ほどですが、例えば将来的に就職を目指したとしても、クリエイターとして就職して食べていくのはハンデの有無を問わずかなり大変なこと。
だから決して夢だけを大きく抱かせるようにはしないように気をつけています。
利用者さんも案外冷静で、好きなことをするために通って体力を整えて、就職は別の所に行くと考えているかたが多い。それぞれのかたがてくてくに来る目的と、人生でどういう現在地にいるのかを一緒に確認しながら、スキルアップや成長についても考えています。
実はてくてくは、利用者さんが毎年100人近く集まる一方で、うち30人ぐらいは辞めるんです。
やっぱり実際にやってみると分かるんですよね。動画やアニメを見るのは好きだったけど、作るのはそんなに好きじゃないな、とか。だから、頭の中で好きなことを探すだけでなく実際にやってみたほうがいいと思っているんです。伸び悩みがあったとしても、人生には別の場所やほかの選択肢があるのだから、それはそれでいいのかなと。

写真=写真工房坂本
――家族など、周囲の身近な存在との関係性についてはどうでしょうか?
桑田 残念だなと思う例としては、てくてくへ来て自分の好きなことに没頭できているのに、家に帰ると家族からはけなされ否定されてしまうかたもいるんです。
20年間ずっと否定の言葉を浴び続けていたら、どんな人でも自分に自信を持てないままですよね。どうせできないとか、やめろとか、否定のメッセージはなるべく減らして、まずは本人が望むようにやらせてほしい。
それから、「自由に決めていいですよ(でもそれは健常者や家族に迷惑をかけない範囲でね)」、「あなたが選んでください(障がい福祉サービスの中でね)」というふうに、中途半端に許容しているようで括弧書きの条件をつけることも何だか残酷に感じます。
そうすると彼らは「障がい者として」の自分を意識し続けて順応しようとしてしまうので、そのかた自身の心が、どんな喜怒哀楽を感じて何に幸福を感じるのかに気づけるような関わり方をしてほしいなと思います。
――障がいの有無にかかわらず、広く子育てにおいて「才能や可能性を伸ばす」ためにも通じることなのかもしれませんね。
一人の人として見れば、相手とフラットに向き合える
――てくてくのスタッフさんも利用者さんにとって大きな存在ですよね。実は皆さん、福祉業界の経験者ではないとか。
桑田 うちのスタッフはほぼ全員、もともとクリエイターなんです。美大の新卒とか、もともとゲーム会社で何か作品を作っていたとか。だから正直、障がい福祉のことは全く分かっていないんですよね。
でも、例えば障がい名を見たとしても正確には理解できないけれど、相手が困っていることや苦手なこと、必要なサポートは話していれば何となくわかってくる。一人の人として利用者さんを見ているというところはポイントだと思います。
同じことが好きな「同志」のような存在でもあるし、中には元アニメ監督とか、有名出版社から漫画を出してますとか、ものすごく技術レベルの高い利用者さんもいらっしゃるので、既存の福祉事業所でありがちな「支援者」と「被支援者」という関係性の上下のようなものができにくいのだと思います。

てくてくのスタッフたち自身も、自然体で日々仕事に向き合っている(写真=写真工房坂本)
過去に10年ぐらい引きこもっていたことがある40代のかたが先日、自力で就職されたんです。しかも「障がい福祉枠」としてではなく、一般枠で。
そのかたはいわゆる「不安障がい」といって、人と話すことが怖くなっていたんですね。自分が話した言葉が相手に正しく伝わらない、相手が話すことも自分は正しく理解できないと思ってしまう。例えば自分が「これが名刺です」と言っても、「いや鉛筆だよね」って言われちゃうような感覚で、言葉が通じない。もう話すことが不安だし、働くことなんて無理でした。
本人に聞いたら、「何か最近、恐怖がなくなったんですよね。てくてくのスタッフがあまりにも普通に話してくれるから、もしかしたら自分も普通の人間なのかもしれないと思ったら、少しずつ会話が怖くなくなってきて、今は普通に話せてます」と。人と人として普通に接することで、結果的にありのままの彼らが引き出されていたんです。
――人と人として。大切なのはシンプルなことなんですね。
桑田 彼らがどういう人生を歩みたくて、そのためには今彼らにとって一時的に何が必要で、てくてくで何を経験できたらいいか、単なるB型事業所として福祉サービスだけを提供しているわけではなく、人生の一部分であることを忘れないようにとはスタッフにも伝えています。
自身のケアや対応について強く要望を出される利用者さんもいますが、彼らが一般社会で自立して生活をしていくことを目指すならば、すべてにそのままこたえることだけが正しいわけではないときもあります。

写真=写真工房坂本
人を、自分を、「手段化」しない働き方とは
――人生の一部分。福祉やクリエイティブの世界にとどまらない視点ですね。
桑田 大きい話でいくと、現代の資本主義や、それに基づく企業経営というものは、やっぱりどうしても人を「手段化」しますよね。極めて巧妙に、合理的に。この構造はとても厄介で罪深いなと思って見ていますね。みんな生きるためにお金が必要で、お金を稼ぐためには雇用関係しかなくて、そこにしがみつき続けざるを得ない。と思い込んでいる。
でも実は、確かにお金は便利ですが、お金に頼る比率は下げられるかもしれないし、お金が必要だとしても稼ぐ方法は雇用関係だけでもないのにな、と。
でもみんなそうだと思い込まされて、自ら進んでこまになっていく。そしてそのために逆算して、学校ではよい成績を取る、いい大学に行く、何かのスポーツがうまくできるほうがよいとか、人が機会に対する手段になっていって、自分自身を見失っている……そんな違和感はあります。
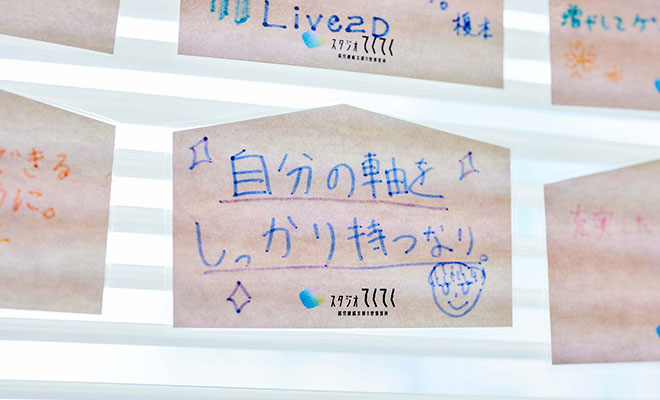
てくてくの利用者たちは、思い思いに「目標」を書き、フロアに掲示している(写真=写真工房坂本)
一応うちのコンセプトとして「世界一納期を守れない(かもしれない)スタジオ」とあえて堂々と出しているのですが、でも実際はちゃんと守るんですよ(笑)。
一生懸命みんな頑張るんですけど、今は笑って済ませてくれる企業さんとお仕事ができているので助かっています。
――当たり前と思い込んでいることが怖くなりますね……。まず、「人を手段化」しないためにはどうしたらよいでしょうか?
桑田 うちでは例えば目的・目標みたいなものはなるべく置かないようにしています。
会社としての方針や状況を伝えるための指標などはスタッフに伝えますけど、絶対に売上を上げろとか、利用者数を増やせといったことは言いません。スタッフが目の前のこと、価値提供にちゃんと集中できるようにする。その結果、僕らが提供するサービスが世の中に受け入れられれば、売上などの数字はついてくるだろうなと思っているので。
もう一つ、会社の「経営者と従業員」とか「会社の内と外」みたいな境界線をできるだけなくせるといいなと。
例えば、グループ会社「てくてくLab」のオフィスは人がいなくなる15時以降は地元にある養護施設の子たちが自由に遊びに来られるようにしていて、うちのPCでお絵描きとか動画制作をしています。一生懸命描いて、作品が完成したら「できた!」って自慢しに来てくれて。子どもは技術の習得が早いですよね。
――もしかしたら将来、スタッフとして働いているかもしれないですね!
桑田 そうなったらうれしいですね(笑)。余っているものは別に会社の内外を問わず無料でシェアして使ってもらえばいいんじゃないかと。八王子の事業所であればフリースクールに遊びに行ったり、高円寺の事業所だったら僕がカフェの1日店長をしに行ったり、囲わずに内外を自由に行き来する。
スタッフも、面白がって自主的に新しいチャレンジをしようとしてくれます。「利用者さんにこんな新しいイベントを考えた」とか、「夢だったVTuberのライブ舞台映像制作を受託できた」とか。
利用者さんだけでなくスタッフも幸せに生きるためには結局、職場にいるときもそれぞれが自分の大切にしたい人生とつながった状態でいられるかどうか。自分を大切にできない人は、人の幸せも大切にできないと思いますし。
一般的に、上司に褒められるため、評価を上げるため……と、「自分で自分を手段化」してしまうと仕事をしても幸せに思えません。自分は何がしたかったんだっけということを常に考えてほしい。
だから、「私の人生に何があれば幸福感を持てるか」とか、「死ぬまでにやりたいこと」などをみんなで言語化してシェアしています。そのためにてくてくという舞台があり、使い倒してもらってかまわないということですね。

2年ほど前までは広島で家業の革製品製造を手伝いつつ、Live2D関連の仕事もしていたというスタッフSさん(20代)。よりクリエイティブに特化した環境を求めて上京し、入社。現在はクライアントと利用者さんとの間に入ってコミュニケーションを取り、各種調整や連携を行っている。「いろんな人と話したり関わったりして視野を広げる大切さに気づきました。これからも職場外も含めてたくさんのつながりを作り、そしてそのつながりを強くしていきたいですね」(写真=写真工房坂本)
この場所で、あなただからできること
――今後目指していきたいこと、思い描いていることはありますか?
桑田 そもそもアニメスタジオやゲームその他の制作会社が多い中央線沿線エリアでサブカル事業を始めたのは、福祉が産業と地続きになってきちんとニーズがかみ合うことが望ましいと考えたからです。
加えて、これは福祉に限りませんが、何か困ったこととかやりたいことがあったときに気軽に助け合える、一緒にやろうよと言える「顔の見える仲」で、あるものをお互いに持ち寄りながら交流できる地域になっていくといいなと思っています。
「居酒屋てくてく」と題して2~3か月に1回、地域の福祉関係者とか学校の先生、企業のかた、たまに議員のかたなどにも来ていただいて、ただの飲み会をしているんです。飲食するとまずは仲良くなる。仲良くなれば、そのあと一緒に何かやることへの心理的なハードルも下がる。損得勘定を抜きにして語り合える。
「居酒屋てくてく」も、養護施設とのシェアも、そんな関係性を作るための草の根活動みたいな感じで続けていきたいです。
――未来につながる仲良し、すてきですね。「居酒屋てくてく」にいつか私もお邪魔したいです(笑)。
桑田 それから「ちょこクリ(ちょこっとクリエイティブ)」といって、近所の居酒屋さんに提案して、掲示物とか大将のバースデーカードとかを配るとすごく喜ばれるんです。
店に飾ってもらっているところに作者である利用者さんを連れて行ったら、店員さんは利用者さんの障がいについて知らないから、「障がい者の」ではなく「個人としての○○さん」という関係性が生まれる。本人にとって、「自分は『クリエイティブなことで喜びを提供できる人』なのかもしれない」という自己認識の引き出しを増やせることも重要ですよね。
僕らはさまざまな問題を最終的にお金で解決しようとしがちです。だから自分自身のことも、自分の能力も、無意識に値踏みしているわけですよね。でも、今仕事にしている能力以外にも何かできるかもしれない。
例えば引っ越しの手伝いとか、子どもを預かるとか。僕らはそれぞれ、お金にできないけど持っている物や力がいっぱいあるのだから、自分を変に値踏みしない、そんな社会になってくれたらいいなと思って活動しています。
――自分でも気づいていないような持ち物や力をお互いに見つけ合えたら、きっとうれしくなりますね。
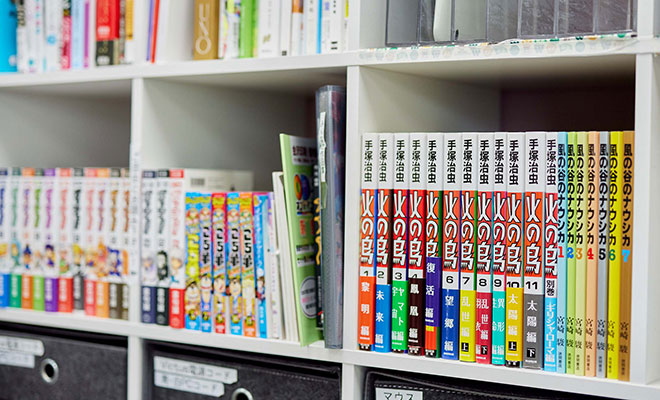
写真=写真工房坂本
いつの時代もサブカルは、タブーのない心のより所
――近年、マイノリティのかたがたに対する理解が進む一方で、排他的な考え方を持つ人もいまだに少なくないように感じています。
桑田 今は本当に日本が経済的に貧しくなりつつあって、圧倒的な勝ち組と貧困層という明確な存在だけでなく、頑張っているんだけど生活はあまり豊かじゃないような層もいますよね。この層はものすごく疲弊しているように見えます。そういう意味では、現代の生きづらさは決してマイノリティに限った話ではないのかもしれません。
でも僕は今の状況を、比較的ポジティブにとらえています。なぜなら、食べ物やエネルギー、その他の物作りなど、生きるために必要な暮らしそのものが循環できるような仕組みを、今ある大きい政府や制度に頼らずに自分たちでやっていこうとする小さなコミュニティのようなものが各地で生まれ始めていて、かつ、そんなコミュニティ同士が互いにつながり始めているという実感があります。
今の時代は過渡期かもしれませんが、人としての豊かさの定義が変わってきて、奪い合うのではなく分かち合う、助け合うという文化が確実に少しずつ広まっている。経済的に合理性で戦うことの限界にみんながようやく気づき始めて、しんどいからこそ、そうじゃない形へシフトしつつあるのかなと。
そこでは障がいがあるかたも含め、対等な仲間として、お互いに持っている物や力を交換しちゃおうという社会になっていくと僕は信じています。

写真=写真工房坂本
――最後にずばり、アニメ・漫画の魅力とは?
桑田 それを語るのはなかなか業界に申し訳ないような……(笑)。アニメや漫画には創造性、想像性はもちろんのこと、タブーが少ないですよね。文化とか宗教とか、ごちゃまぜになっていてもちゃんと表現できる。
だから僕は、漫画とかアニメから人生を学んできました。「生と死とは何か」とか、日常の話題としてタブーになるようなことも扱うじゃないですか。それをエンタメに昇華し、文学性も保って形にできているというのは、これはもうすごい芸術だなと。
海外のLGBTQのかたも、日本のアニメ、VTuber、ボーカロイドといった文化によっていやされるそうです。自分の嗜好や気持ちはそのままでよかったんだと認められたように思える。多様性に対する許容範囲は広い気がします。
てくてくがサブカルにこだわる理由も、必ずいつの時代にも「サブカルチャー」という存在はメインカルチャーに対して存在するので、そこをちゃんと居場所として大切にしていきたいなと思っているからです。
ここにいていいんだよ、だけどメインでなくてもいい。10年後、20年後に、時代とともに「サブカル」の内容も移り変われば、また全く別のことをしているかもしれません。