
がんばらない更年期のススメ。もっと軽やかに、しなやかに、未来を描こう
不安やイライラを抑えられなかったり、理由もなくどうきがしたり、急に汗が吹き出したり。閉経前後の約10年間、こうした「更年期症状」に悩まされる女性は少なくありません。少しでも楽に乗り越えて、軽やかに次のステージに進むにはどうしたらいいのでしょうか? 産婦人科専門医・高尾美穂さんに、そのヒントを伺いました。
- 暮らしと社会

不安やイライラを抑えられなかったり、理由もなくどうきがしたり、急に汗が吹き出したり。閉経前後の約10年間、こうした「更年期症状」に悩まされる女性は少なくありません。少しでも楽に乗り越えて、軽やかに次のステージに進むにはどうしたらいいのでしょうか? 産婦人科専門医・高尾美穂さんに、そのヒントを伺いました。

世の中にさまざまな社会課題があることは知っていても、なかなか行動できない――「社会を変えるには、そんな“僕みたいな人間”でもやってみたいと思える仕掛けが大事です」と話す小国士朗さん。NHKのディレクター時代に企画した「注文をまちがえる料理店」にはじまり、がんの治療研究を支援する「deleteC」などを手がけてきた小国さんに、プロジェクトの生まれた背景や軽やかにアクションを起こすために大切なことをうかがいました。

「イエロードッグプロジェクト」という、さまざまな事情で散歩がしづらい犬たちを助けるための活動が広がっています。散歩中の犬が黄色いリボンをつけていたら、「近寄らないで」のサイン。犬と暮らしている人も、暮らしていない人も、地域のみんなで作る思いやりの形があります。

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」。被災地となった石川県能登半島では、長い歴史のなかで工芸や工業が発展してきました。発災から半年がたつ頃、さまざまな立場でものづくりに関わる方々に、ここまでの歩みと思いを聞きました。
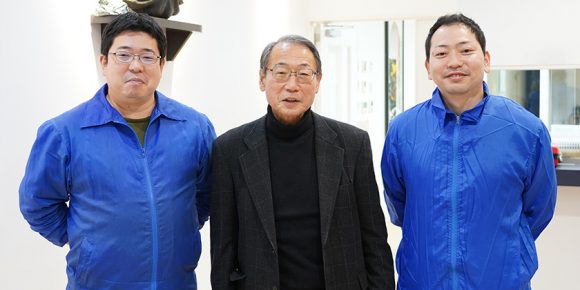
東日本大震災から13年がたちました。東北の地には、「あの震災は何だったのか」という答えの出ない問いに向き合いながら歩み続ける人たちがいます。宮城県東松島市の水産加工会社・高橋徳治商店を訪ねました。

2023年2月に発生したトルコ・シリア大地震。パルシステムによる「緊急支援募金」は、現地で支援活動を行う7団体に贈られました。そのひとつ、公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの福原真澄さんに、支援や現地状況の詳細、今求められていることを伺いました。

がん経験者のインタビューを発信するYouTube番組「がんノート」。立ち上げたがん経験者・岸田さんに、患者が経験した情報の貴重さと、がん患者であることを抵抗なく話せる社会の必要性について、聞きました。

「新型コロナ災害緊急アクション」に届く、SOSのメールが止まりません。一桁台の所持金、綱渡りの毎日、死への恐怖…。貧困支援の現場で聞こえてきたのは、「コロナだけが原因ではない」という声でした。

未曾有のコロナ禍の中、さらなる格差と分断、対立が深まっています。これまで暮らしや社会の課題に向き合ってきた生協は、どんな役割を果たせるのか。新旧の理事長が語り合いました。

新型コロナウイルスによって社会は、大きな変化を迫られた。暮らしや地域の課題に取り組んできた生活協同組合は、コロナ禍でどのような役割を果たすのか?新旧の理事長が語り合いました。

新型コロナの影響で、非正規雇用など不安定な労働形態にある人たちの状況が深刻です。東京都庁下で食事提供や相談会を行う「新宿ごはんプラス」には、3月以降、仕事や住まいを失い、助けを求める人が増えています。

多彩な芸能活動のさなか、芸歴を上回る歳月を、慈善活動に捧げてきた俳優・杉良太郎さん。数えきれないほどの「助けて」の声に向き合った杉さんが考える、コロナ禍後の生き方とは。

空き家・空き室が増える一方、家を借りたくても借りられない人が多くいます。そうした人を支援するため、「居住支援」の仕組みが動き出しました。誰もが安心して暮らしていくために何が必要なのでしょうか。

児童養護施設や里親家庭など社会的養護のもとで育つ子どもたちの中には、虐待をはじめとするつらい経験をしている人も多くいます。彼らに寄り添うべく、首都圏の民間団体が支援のあり方を模索しています。

人と地域、自然とのつながりを再生し、自分たちの手に経済を取り戻そうという動きが世界じゅうで起きています。食や農業の在り方を見直す取り組みに注目しながら、「しあわせの経済」の在り方を考えました。