
出産や子育ての不安も喜びも、何でも話せる場を作りたい。助産院から生まれた母と子のサロン
待ちに待った赤ちゃんとの暮らし。いざ始まってみると、思うようにならないことは多く、気持ちが不安定になることも。そんなお母さんたちを温かく支えようと、サロンを開設した助産院があります。
- 暮らしと社会

待ちに待った赤ちゃんとの暮らし。いざ始まってみると、思うようにならないことは多く、気持ちが不安定になることも。そんなお母さんたちを温かく支えようと、サロンを開設した助産院があります。

北海道東部に位置する野付漁業協同組合と生協パルシステムが取り組んできた植樹が、2018年6月に1万本を達成しました。なぜ、漁業を生業とする漁師たちが植樹を続けてきたのか。その軌跡を追いました。

独特の風味とうまみで知られる八丁味噌を400年以上造り続けてきた2社の老舗メーカーが、「八丁味噌」と名乗れなくなるかもしれない事態に直面しています。一体、何が起きているのでしょうか。

私たちの食卓には、作り手の顔が見えない食品が並びがち。そんな現状を変えていこうというムーブメントが「スローフード」運動です。国内外で取材を続ける作家の島村菜津さんにその可能性を聞きました。

東京・新宿から30分余りの場所にある「いなぎめぐみの里山」は、パルシステム東京が運営する場所。今年度から、竹林の整備活動を通して健康づくりも目指す企画「グリーンジム」が始まりました。

『へいわって どんなこと?』は、絵本作家の浜田桂子さんが、日常の中にある平和の素敵さを描いた著作です。日中韓の作家による画期的な絵本作りのプロジェクトで育まれた思いとは、何だったのでしょうか?

「この暑さで、食欲がわかない!」と泣きつく編集部の二人。食文化史研究家・魚柄仁之助さんが教えてくれたのは、マンネリをも解消する! 粉を使った涼しげな料理のワザでした。
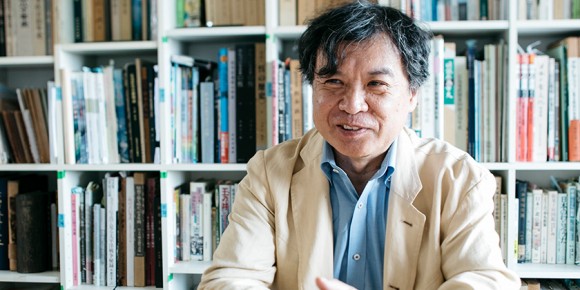
大ヒット映画『この世界の片隅に』の上映が、途切れることなく続いています。大戦前後の広島県・呉を舞台に淡々とつづられる人々の「普通の暮らし」が、なぜこれほどまでに心をつかむのでしょうか。終戦の日を前に、監督・片渕須直さんに聞きました。

食を育むふるさとと作り手に寄り添い、菓子作りに込める菓子研究家の長田佳子さんがパルシステムの産地を訪ねます。4軒の酪農家が守る「低温殺菌牛乳」との出会いからどんな景色が見えてどんなお菓子が生まれたのでしょうか?

認知症となった母との日常生活を撮影してきた関口祐加さん。自分の老いとも向き合う関口さんが、映画『毎日がアルツハイマー』シリーズの最終章で選んだテーマは、やがて誰もが迎える「死」のあり方についてでした。

福島県福島市にある土湯温泉。震災後は観光客が激減する中、地熱発電による町おこしが進んでいます。2017年12月から「パルシステムでんき」の発電産地に加わった「株式会社元気アップつちゆ」を訪ねました。

70年間、軍隊を持たずに非武装・中立を貫いてきたコスタリカは、なぜ「地球幸福度指数」の世界ランキングで何度も1位に輝いているのか? 映画『コスタリカの奇跡 ~積極的平和国家のつくり方』の監督に聞きました。

つけてしまったシミ一つ、うっかり空いた穴一つ……。衣服の傷みを手軽に楽しく「お直し」する術を伝える暮らしの装飾家・ミスミノリコさんに、小さなひと手間で日々を彩るアイデアを伺いました。

「奇跡の海」と呼ばれるほど希少な自然を残す山口県上関町が、原発建設計画地となって35年以上。賛否を巡って対立と分断を余儀なくされてきた住民たちの意識は今、大きく変わりつつあるといいます。

障がいのある・なしに関わらず、みんなで楽しめるユニバーサルデザインの絵本を広げたい。全盲の娘さんがいる母親の大下利栄子さんは、既存の絵本に透明の点字シートを挟んだ「UniLeaf Book」を作る活動を続けています。