視察で見えた、非遺伝子組換え作物確保のむずかしさ
「非遺伝子組換え(Non-GMO)作物を確保し続けることは、予想以上に厳しくなりつつあると感じました」。2013年9月、遺伝子組換えの実態を調査するため、アメリカ視察に臨んだ渋澤温之(パルシステム連合会 商品開発本部長)は、そう言って表情を曇らせます。
非遺伝子組換え作物の栽培は、畑での区分管理はもちろん、遺伝子組換えなら手間が省ける雑草や害虫の対策に加え、集荷の日時が指定されるなど、生産者に大きな負担が。渋澤が現地で痛感したのは、そうした負担に加え、生産者が抱えているリスクの高さでした。

パルシステムはアメリカでの遺伝子組換えの実態を調査するため、現地の商社、種子メーカー、生産現場を視察した
「かつて非遺伝子組換えとうもろこしを栽培していたという生産者は、集荷時の検査で遺伝子組換え作物の混入を指摘され、受け入れを拒否されてしまったことがあったと悔しそうでした。近隣の畑から遺伝子組換え作物の花粉が飛んできて混入したようですが、はっきりとはわかりません。彼は『もう、これ以上続けられない』と、非遺伝子組換え作物の栽培継続を断念したそうです。農場の規模が大きいだけに、損失もけた違い。『非遺伝子組換え作物の栽培を続ける』という意欲的な生産者がいないわけではありませんが、そこには相当高いリスクがあることを実感しました」(渋澤)
実際、アメリカ農務省の発表によると、アメリカで作付けされたとうもろこしにおける遺伝子組換えの割合は2000年に25%だったのが、2013年には90%と激増。しかも、「非遺伝子組換えとして栽培されたものでも、分別物流されているものはわずかしかない」と、ある穀物商社の担当者は話します。

「需要があれば非遺伝子組換えを作り続ける」という生産者がいる一方、「これ以上は続けられない」と話す生産者も
畜産飼料の輸入依存度を下げ、遺伝子組換えに頼らないしくみへ
決して楽観視できない、アメリカにおける非遺伝子組換え作物の栽培の実態。穀物としてのとうもろこし(※1)のほぼ100%を輸入に頼り、その約9割がアメリカ産という現実を抱える私たちに、「遺伝子組換え作物を使わない」という選択はあるのでしょうか。この問題について考える際に切り離せないのが、輸入とうもろこしの最大の用途である家畜の飼料です。
商品づくりにおいて、遺伝子組換え作物及びそれを主原料として使用した食品に対して反対の立場をとるパルシステムでは、畜産飼料についても、可能な限り非遺伝子組換え原料の使用を進めてきました。しかし近年、バイオ燃料や新興国への需要拡大などにより、とうもろこしの国際価格が高騰。流通量の少ない非遺伝子組換えとうもろこしは、確保が困難なうえにコスト負担も増しており、産地の経営はギリギリの状態に置かれています。
畜産飼料を輸入穀物に頼っていたままでは、遺伝子組換え作物を排除することはなかなかできません。そこでパルシステムが取り組んでいるのが、国産原料を使った飼料への転換。たとえば『日本のこめ豚』や『産直こめたまご』では、国産の飼料米の配合率を高めているほか、『コア・フード牛肉』ではおからやじゃがいものかすを飼料に活用するなど、飼料の自給率を上げていくしくみを産地とともに模索しています。豚肉の産地のひとつ、ポークランドグループ代表の豊下勝彦さんは、「豚の健康や肉質の変化などに配慮しながら飼料米の配合率をさらに増やしていけば、輸入とうもろこしの割合を上回ることも不可能ではない」と意欲を燃やします。

ポークランドグループ(秋田県)は、仕上げ期の飼料の10%に飼料米を配合した『日本のこめ豚』を生産している
「私たちは、できることから始めていかなければいけない。非遺伝子組換えにこだわる産地を支えながらも、飼料の自給率を上げる取り組みを進めることは大変意義があることだと、アメリカ視察を経て改めて認識しました」と渋澤は語ります。
※1:家畜の飼料や加工食品、コーンスターチ、食品添加物の原料に使われる。
意思ある消費者と生産者との連携が対抗する力に!
また、畜産飼料の自給率向上と並んで「今こそ、その価値に注目したい」と渋澤が示すのは、パルシステムの『菜種油』の取り組み。というのも、日本で流通している菜種の89%(※2)が遺伝子組換えといわれるなか、パルシステムの『菜種油』は発売以来一貫して、非遺伝子組換え原料を使用してきたのです。それを可能にしたのは、「産直」による生産者との連携――。
『菜種油』の原料は、開発当初、カナダ産の菜種を使用していましたが、カナダが遺伝子組換え技術の導入に積極的であることから、1999年にいち早く原料産地をオーストラリアにシフト。オーストラリアでも次々に遺伝子組換え作物の栽培認可が下りるなか、2006年には、栽培を禁止している南オーストラリア州カンガルー島で現地の生産者と産直協定を結び、原料を確保してきました。
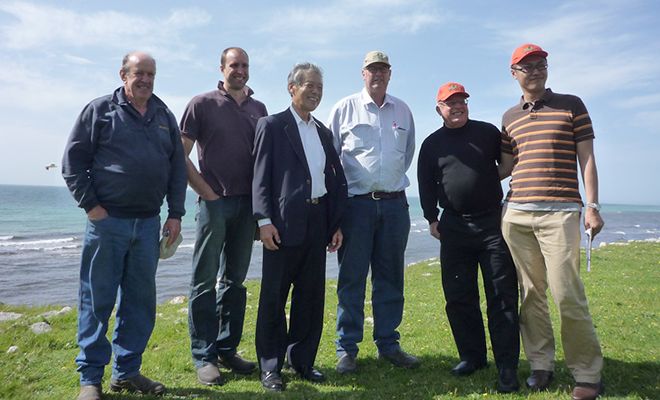
5年もの歳月をかけて実現した、南オーストラリア州カンガルー島の生産者との産直提携。写真は、初期の産直を築き上げたメーカーの平田産業(有)と地元生産者のみなさん
それまで、消費者と直接やりとりする経験のなかったカンガルー島の生産者たち。「産直」と聞いても、最初は「本当に自分たちの菜種を買い続けてくれるのか」と疑心暗鬼だったといいます。しかし、製造元のメーカーとともにていねいに交流を重ね、「非遺伝子組換えの菜種がほしいんだ」と熱心に意思を示し続けた結果、生産者も「日本の消費者のために」と、非遺伝子組換え菜種の栽培に取り組んでくれるようになったのです。
「パルシステムとの産直が大きな契機となり、南オーストラリア州政府は、少なくとも2019年までは禁止を貫く方針を示しています。意思ある消費者と生産者とがつながれば、遺伝子組換えを進めようとする力に対抗できる。そのことを示す貴重な事例だと思います」(渋澤)
ここで改めて思い出したいのは、「市民バイオテクノロジー情報室」代表・天笠啓祐さんの、「日々の買い物を通して、私たちは遺伝子組換え食品を避けることができる」との言葉です。
[TPPで迫る食の危機(3)]食卓に忍び込む「遺伝子組み換え」―天笠啓祐さん
自分がいま口にしようとする食べ物は、誰が、どこで、どのような方法で作ったものなのか。この食卓までどのように運ばれてきたのか。この食べ物は、何とつながっているのか。まず関心を持ち、知り、食を他人任せにしない――。一人ひとりの日々の買い物が、社会へ、世界へ、そして未来へとつながっているのです。
※2:輸入元の国における2012年作付面積の割合と2010年の日本の輸入割合をもとに試算(資料:アメリカ農務省、農水省資料/試算:天笠啓祐さん)




