原発事故を忘れてしまっている人たちにこそ見てほしい
――これまで多くの話題作を世に送り出してきた奥山さんが、この映画について、自ら配給に名乗りをあげたのはなぜですか?
奥山 NHKの朝の番組で、映画のことが紹介されていたのを偶然見かけたことがきっかけでした。放映はほんの短い時間だったのですが、ワンショットかツーショットだけで、自然にしみ込んでくるような感じがいいなぁと思ったんです。
とくに印象的だったのが音。開け放たれた窓辺でカーテンがたなびいている音、町のアナウンスの響き方、商店街のシャッターが揺れる音……人気のない静けさを際立たせるデリケートな音の使い方に感心した。サウンドエンジニアの方が監督されたという説明があって、ああ、なるほどと合点がいったのです。
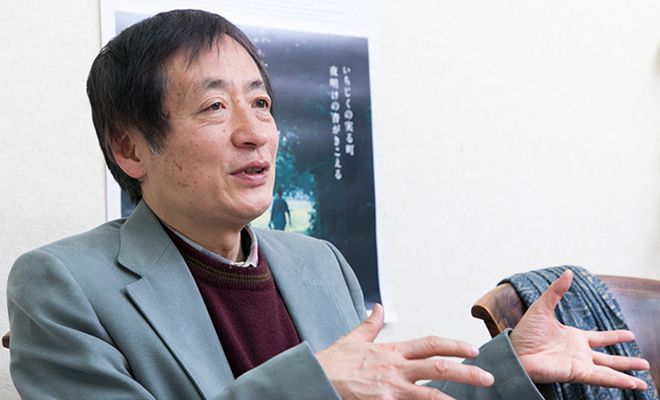
本作で配給プロデューサーを務める奥山和由さん(写真=疋田千里)
正直言って、僕は、原発問題や福島のことに関してこれまで基本的にはさわってきませんでした。だから最初に興味が湧いたのもこのテーマだったからではなく、純粋に映画的な角度からでした。とにかく全編を見たくなって、すぐにNHKやベルギー大使館に電話したら、その日のうちに鵜戸さんと連絡がとれたのです。
――実際に作品をご覧になって、印象はいかがでしたか?
奥山 作為的な押し付けがましさが一切なく、そこにある事実だけをきちっときれいに飲み込んでいるというすがすがしさがあった。撮られている人たちにもどこかでカメラや音声を意識するような“撮られている感”がまったくないんですが、監督であるジル・ローランさんの息づかいや目線みたいなものが見事にスクリーンから伝わってくるのです。

©CVB / WIP /TAKE FIVE – 2016 – Tous droits reserves
福島や原発に対して明確な考えを持ってこなかった僕自身でも、一観客として深く感じるものがありました。あれだけの大きな災害があったなかで、人間が自ずと学ばざるを得ないこと、「育む命の実感」とでもいいましょうか、そういうものに触れさせてくれている。同時に、自然の営みや命の循環みたいなものに対して、原発のような人為的な力を強引に働かせようとする人間の業がいかにむなしいものであるかも見えてきたんです。
声高に“反原発”を語る映画ではないけれど、僕のように原発問題から遠ざかっている人たち、ややもすれば原発事故があったことさえ忘れてしまっている人たちこそ見るべき映画だと思った。日本での公開が決まっていないという話だったので、ある種の義務感にかられてというとキザですが、運命的なものを感じて関わらせていただくことにしたのです。
自然と人との絶えない関係。そこに希望がある
――奥山さんがとくに印象に残っているのはどんなシーンですか?
奥山 避難指示解除が予定されている地域で、自宅に戻ることに決めた女性の家に主婦仲間が集まり、お茶を飲みながらおしゃべりをしたり、みんなで歌ったりしているシーンですかね。
出てくる人も土地もとにかく明るいのが好き。何にも手を出しようがなくて、絶望みたいなものが襲ってくるなかでも、「しおれていてもしょうがないから、今日を生きるか」って、夫婦で畑を耕して立派なナスができたって喜んだり、並んで座ってテレビを見たり。そうして1日1日を積み上げている。テレビを観て「きゃっきゃ」と笑っているおばあちゃんの隣で、おじいちゃんが笑っている。それでいいんだなって思えるんです。

©CVB / WIP /TAKE FIVE – 2016 – Tous droits reserves
「この町はいずれ完全に死の街になるけれど、何十年かたてば必ず元に戻る」という登場人物の言葉は象徴的です。何があっても自然と人間との間の“育む・育まれる”関係というものは決して消えない。たとえば放射能のような人為的なものがある種の絶望を瞬間的につくったとしても、それに負けないだけの自然の大きな流れがあるということを信じさせてくれる。希望を感じさせてくれるんです。
「デート中にレコーダーを取り出すくらい、音にこだわる人でした」
――パートナーとしての鵜戸さんから見て、ジルさんとはどのような方でしたか?
鵜戸 つきあい始めの頃に私が惹かれたのは、穏やかさと刺激を好む冒険心みたいなものが同居しているところでした。いっしょにいて落ち着くんだけれど、たとえば、この景色はきれいだとかこの映画の撮り方はどうだとか、常に自分なりの見方を持っている。完成した映画を見て、そんな最初の印象を思い出しました。淡々としているんだけど、同時に訴える力というか心を揺さぶる強さがある。

鵜戸玲子さん(写真=疋田千里)
常々「僕はカルチャーとネイチャーが好きなんだ」とも言っていましたね。映画のなかに出てくるおはぎにとまる蜂やクモの巣にかかった蝶のシーンは、生きものの美しさをリスペクトしていたジルらしい。この映画には、あますところなくジルが好きだったものが入っていて、ある意味、“ジルのよみがえり装置”だと思っています。
音に関するこだわりも、彼独特でした。初めて来日していっしょに明治神宮に行ったとき、樹に風があたって、葉っぱがざわざわしていたんです。そうしたら、何をしたと思いますか? おもむろに小さなレコーダーを取り出して、録音し始めたんです。観光に来て音を録っている人というのは初めてで、びっくりしました(笑)。

撮影中のジル・ローランさん
――試写会などでは、どんな反応がありましたか?
鵜戸 最初はこれをいろいろな人に見てもらうたびにジルがよみがえるんだという気持ちだったのですが、試写を重ねていくうちに、だんだん私が思っている以上の伝わり方をしていると感じるようになりました。
この映画を世の中に出すために、あえてジルがテロで亡くなったことや福島のドキュメンタリーであることをお話しているのですが、試写会の後で感想をうかがうと、「自分の家族について考えました」「人生について考えました」「住む場所について考えました」と、ご自分に引き寄せたコメントが多かった。なかには「神様がつくった映画としか思えない」とまで言われる方もいました。
ジルのお姉さんは、ジルが育ったベルギーの町の風景に似ていると言っていましたし、日本の方も、おばあちゃんの家を思い出すとか自分のふるさとの風景にそっくりと言われる。そういう方たちの反応と自分の気持ちを重ねてみると、この映画のテーマは、広く、人と土地、人とふるさとの結びつきなのだと、いま、改めて感じています。

©CVB / WIP /TAKE FIVE – 2016 – Tous droits reserves
自分以外の人の大切な場所にも想いを馳せたい
――『残されし大地』という邦題は、日本での公開にあたって鵜戸さんがつけたそうですね。どんな想いでこのタイトルにしたのですか?
鵜戸 原題を訳すと「見捨てられた大地」となるのですが、見捨てたんじゃなくて、愛着があっても戻れないというのが現実ですよね。物体としての人はそこにはないけれど、想いはそこにある。「見捨てられた」に引っ掛かりがあって考えているうちに、「ああ、残されたってことなんじゃないか」と。
私自身も「残されし家族」なんですよね。ジルがいなくなって一時は失意のどん底にあったけれど、一つひとつ積み上げてここまで生きてきたし、生きていれば結構明るい出来事も多い。「残されし」に、自分自身も重ね合わせてみたんです。人生や世界ってそういうものだと思いたいなって。

写真=疋田千里
――いよいよ日本での公開ですね。いまの心境をお聞かせください。
奥山 僕はビジネスのためにがむしゃらに売るという仕事もしてきたんだけど、この映画については、「存在してほしい」という気持ちが強いんです。この映画には、存在しているだけで広がっていける生命力がある。そうして出会えた人と握手をして向き合って。そうすれば、必ず、大地と人との営みは永遠に消えることはないという希望を伝えてくれるはずです。
鵜戸 生まれ育った所とは限らないけれど、だれにも自分の愛着をもった土地やふるさとがありますよね。私にとって3年半住んだだけのベルギーがそうであるように。そして誰もが、その大事にしている場所が傷ついたら悲しいと思うんです。
自分と自分の愛着ある土地とのつながりを思い出し、それと同時に、できれば自分の目の前にいる人にもかけがえのない場所があることに想いを馳せたい。皆がそういう想像力を持てたら、もしかしたら世界平和も実現するんじゃないかな。ジルは、「世界平和」という旗を掲げてこの映画を撮ったわけではないけれど、いつも心にはその理想があった。この映画から、そんなメッセージが自然に広がっていけばうれしいですね。




