認知症ケアは一人一人違うもの
――『毎日がアルツハイマー』シリーズの前作では、認知症ケアの考え方を取り上げていました。今作にもつながるテーマだと思うのですが、改めて「パーソン・センタード・ケア」について教えていただけますか。
関口 パーソン・センタード・ケアは、認知症である本人を尊重して、その人の立場になりながら、何が不安にさせているのかに気づき、どんなニーズがあるのかを理解した上でケアをするものです。だから、認知症という病気は同じでも、ケアは十人十色。英国で撮影した際、認知症ケア・アカデミー施設長のヒューゴ・デ・ヴァール先生は「探偵になる」ということを教えてくれました。

ヒューゴ・デ・ヴァール先生を訪ねる関口祐加さん(右) © 2018 NY GALS FILMS
パーソン・センタード・ケアは、巡り巡って介護している私のためにもなるんですよ。例えば母のデイサービス一つとっても「忙しいから行ってほしい」と言ったら、邪魔にされていると思うじゃないですか。だから、本人が行きたくなるように仕掛けるんですね。
私の場合はケアマネジャーに頼んで、母が行きたくなるようにイケメン介護福祉士を探してもらいました。お願いしてから2週間ぐらいして「いました~!」って(笑)。本人が楽しいと感じられることが大切です。そうすれば、私も安心して自分の時間が作れます。そのためにはイマジネーションが必要不可欠なんです。
――その人の気持ちになって想像することが大切なんですね。
関口 うちには何人ものヘルパーさんが来ましたが、ほとんどの人が母の部屋を見て「あらっ、ぐしゃぐしゃね」と言いました。なぜ部屋がぐしゃぐしゃなのか。それは、どこに置いたのかを忘れるからですよね。だから、全部出しておく。それをヘルパーさんの仕事とばかりに片づけてしまう人は、認知症のことを全然分かっていないのではないでしょうか。
そうやって母の立場で考えたら、「そりゃそうだよね」って分かってくることが多々あります。なぜ怒っているのか、なぜ泣いているのか、その理由を考えないと認知症ケアは難しいです。

母・関口ひろこさん(左)と © 2018 NY GALS FILMS
距離が近い家族だから難しい
――映画の中で、関口さんがいつも明るくユーモアたっぷりにひろこさんに接している様子は、これまでの認知症介護のイメージを変えるものでした。
関口 母は認知症になる前は良妻賢母でまじめ、私とは性格が真反対でした。もし母と私が同級生だったら、絶対に友達にはならないタイプ!(笑) 母娘といっても距離感があるんです。特に私がカメラで母を撮っているときは被写体として観察しています。だからこそ、色々な介護のアイデアが浮かぶんですよね。
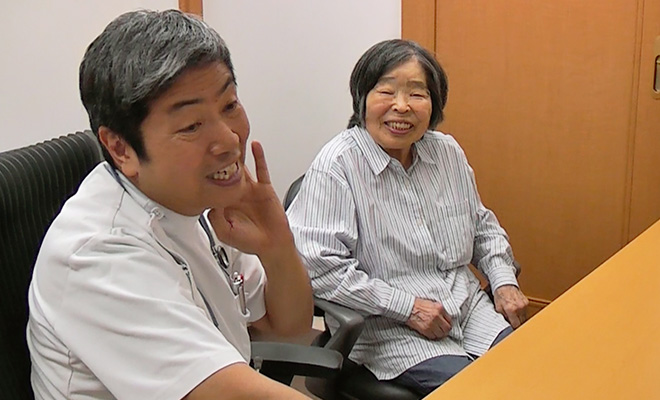
脳神経外科のテストを受ける母・ひろこさん(右) © 2018 NY GALS FILMS
介護って、よくいわれるような「愛」とか「人のため」だけでは長続きしないと思います。そういう情的なことではなく、理性と距離が必要。なかなか家族にはできないことかもしれません。「どうしたの? しっかりして」「前はあんなに出来たのに」ってなっちゃうと思います。
介護において問題が起きるのは「介護される側」ではなくて、「介護する側」が自分の強い思いで「介護される側」を動かそうとするときですね。気持ちは分かりますけれど、摩擦が起こりやすい。家族による介護だとどうしてもそうなりやすい。ひとりで抱え込まずに、介護保険を上手に使って外部に助けを求める。それが、楽な介護につながる一歩です。

写真=疋田千里
母にも、私にも死はやって来る
――これまで認知症やそのケアについて取り上げてきましたが、シリーズ最後となる今作では、どうして「死」について取り上げようと思ったのでしょうか。
関口 実は、最初からこのテーマにしようと決めていたわけではありませんでした。2014年に、私は両股関節の全置換手術を受けたのですが、その入院中に山田トシ子さんと同室になったことが映画の方向性を大きく決めてくれました。山田さんはオープンな性格で、すぐに意気投合しました。私は「病棟の母」と呼んでいたんですよ。

入院中の関口さん © 2018 NY GALS FILMS
彼女はその後、緩和ケア病院に入院することになります。緩和ケア(※1)ということは、延命措置をしないということですよね。そこで最期を迎えられましたが、そのときご家族から「眠りながら亡くなりました」と言われました。でも、その意味が私にはいま一つ分からなかったんですね。山田さんの死をきっかけに「死に方」について深く考えるようになりました。
認知症の母の場合は、自分の生死について自分では決められません。私が母の命を預からなければいけない。そんな母にも私にも、死は平等にやってきます。「どうやっていい死を迎えられるか」を考えたいと思いました。それで、愛媛の託老所「あんき」を訪ね、英国の認知症ケア・アカデミー施設長のヒューゴ先生を再訪し、スイスの自死幇助(ほうじょ ※2)クリニック院長のエリカ・プライチェク先生に会いに行ったのです。
※1:生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を想起に発見し、的確なアセスメントと対処を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を改善するアプローチ(WHO:世界保健機関による緩和ケアの定義〈2002年〉より)。
※2:本作品中では患者の意思に基づき、致死薬物の処方、準備を医師が行い、患者自身が服薬、投薬し、死に至ることをさす。

写真=疋田千里
――この映画は、さまざまな「死の選択肢」を巡る旅でもありますが、最初は緩和ケアへの疑問から始まったんですね。
関口 エリカ先生にいちばん聞きたかったのも緩和ケアのことでした。エリカ先生は正直に緩和ケアの問題は、呼吸が苦しくなることや痛みや死への恐怖をコントロールすることが難しいと教えてくれました。そこから「ターミナル・セデーション」(※3)のことを知ったんです。
ターミナル・セデーションは薬で人工的に意識を低下させて眠らせ、そのまま亡くなる方法です。実は、日本でもやっていることですが、医療的にはグレーゾーンな行為で、あまり公には言われていません。
ただ、最近では、だんだんと医師が家族に説明をし、本人や家族の思いを確認することも増えてきているようです。
※3:本作品中では終末期の患者の苦痛緩和を目的として、言語的・非言語的コミュニケーションができないような深い意識の低下を死亡するまで継続して維持する鎮静をさす。
死に方のパーソン・センタード・ケア
――スイスの自死幇助クリニックのエリカ・プライチェク先生は、「最期は患者さん自身が決めることが重要」だと話していらっしゃいますね。
関口 自死幇助の場合は、非常に明確です。私も疑似体験をしましたが、医者が致死薬物の処方と準備を全部してくれて、最後に自分で点滴のスイッチを押すんですよ。しかもこのスイッチが、ちょっと硬い。最後の最後まで自分の意思を確認できるようになっているという訳です。結構、ビビリましたね。最期の決断は、医師ではなく、自分自身です。もちろん、やめたっていいんですよ。

エリカ・プライチェク先生を訪ねる関口さん © 2018 NY GALS FILMS
安楽死(※4)の場合は医師が絶命させます。私は安楽死には興味がありません。自分の命の全権を医師に譲渡したくないと考えています。オランダは安楽死が合法化されていますが、若い医師は、手がブルブル震えたりするそうです。イギリスのヒューゴ先生は「これ以上苦しむことができない病状もあるから安楽死を否定しない」とおっしゃっていますよね。
どんな死に方がその人にとっていいのかを考えることは、死に方のパーソン・センタード・ケアではないでしょうか。答えは本当に十人十色。介護と同じように死に方もその人の立場で考えたいものです。
私自身、母の介護の終わりに死があることを意識するようになりました。よく「終わりなき介護」と言われますが、母が突然倒れた時、介護は一寸先は闇で、必ず終わりが来ることを痛感しました。私は「終わりからの介護」を考え、母にはゆる〜い介護をしています。
※4:本作品中では患者の意思に基づき、医師が致死薬物を投与・注射し、死亡させることをさす。
正解がないから、考えるしかない
――その選択肢の一つとして取り上げていたのが、愛媛の託老所「あんき」です。お年寄りがそれぞれ思い思いの場所で過ごしていて、食器の片付けもしていました。
関口 あんきでは、扉も窓も開けっ放し。私が理想とする「ゆるい」介護のいい例です。栄養士もいなくて、普通の家庭で食べるような食事を施設長自ら作っている。お年寄りにがちがちの管理はしないという強い意思ですね。ここではまさに「終わりからの介護」が自然に実践されています。

託老所「あんき」のようす © 2018 NY GALS FILMS
――あんきを運営する中矢暁美さんの「最後まで本人の身体で動いて、食べて、そういう力がなくなったときが死ぬとき」という言葉が印象に残っています。
関口 中矢さんは「満足死」とおっしゃっているんですが、それは、家族のことも含めて最後の時を考えているんですよね。本人だけではなく、家族も後悔が残らないように色々と「創意工夫」をする。それが、あんきの考える「満足死」なんです。
――どんな最期を迎えたいのかは、本人の希望がまず尊重されるべきだと思いますが、認知症の場合には、家族がその人にとっての「いい死」を考えることになりますね。
関口 母の場合は、自死幇助という選択肢が目の前にあっても、もう選ぶことができません。私が母の命の責任を担わないといけないという重さは、介護を始めたときからずっと感じていました。介護する側は、自分が常に圧倒的な立場にあるということを決して忘れてはいけないと思っています。
「どんな死がいいのか」には正解がない。その人との関係性のなかで考えていくしかありません。まさにパーソン・センタード・ケアな死に方を考えるということですね。これだという答えは見つからないかもしれない。しかし、考えてやるだけやったというプロセスがあれば納得できることもあるかもしれません。何もしないで医師まかせにしたら、あとで後悔するのではないでしょうか。

母・ひろこさんと © 2018 NY GALS FILMS
――ご自身の死についてはどう考えていますか?
関口 まだ分からないです。でも、最期に自分が死ぬときの映画を撮ろうと決めています。今作品の編集助手にもう頼んでいて、撮ったものを編集してくれることになっています。私はスイスのエリカ先生の自死幇助団体「ライフサークル」のメンバーになっているので、すでに自死幇助ができる権利を持っていますし、息子にも伝えています。最期にどういう選択をするのか、それを自分でも知りたい。もし認知症になったら誰を信頼して介護を頼むのかも大きな問題です。そんな様子をすべて映画にしたいのです。
タブーだからこそ、オープンに話したい
――普段の生活で、こんな風に死について話す機会はほとんどありません。日本では、最期を病院まかせにしてしまうことも多いのはないでしょうか。
関口 死のことは誰だって話したくないですよね。それは日本でも欧米でも同じだと思います。死はタブーだし、オープンに話すハードルがすごく高い。だからこそ、今作品を通してオープンにしたいと思っているんです。

写真=疋田千里
問題の根幹にあるのは、死が遠くなってしまったことだと思います。母が若かった時代は、年をとって食べられなくなったら、死んでいくのが当たり前でした。ところが、今は医療技術が発達したこともあって、死ぬことがそんなに簡単ではなくなってしまった。
でも、自分たちが死んでいくことをきちんとイメージするのは、決してマイナスなことではないと思います。それには、まず老いを受け入れ、次に死にゆく自分の最期の時を考える。そのための映画になれたら、こんなにうれしいことはありません。











