産地・生産者と組合員をつなぐ交流の危機
生協パルシステムの「産直」は、産地直送という意味ではない。食料流通の手段に加え、日々の暮らしの中で、「作り手」と「食べ手」が共に支え合う関係を目指す活動すべてを「産直」ととらえ、農(作り手)と食(食べ手)をつなげるために、産地との交流活動を続けてきた。
例えば、食べ手が作り手の現場に直接足を運ぶ産地交流。現場の空気にふれながら、生産者の生の声で苦労ややりがいを聞くことには、観光では得られない、食べ物の考え方や選び方を変えてしまう力がある。長年の活動でそれを実感してきたからこそ、パルシステムは交流を最重要な活動と位置づけ、途切れさせることなく続けてきた。

産直産地「無茶々園(愛媛県)」での産地交流の様子(2019年12月)
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、活動に暗雲が立ち込める。
「年間70回ほど行ってきた産地と組合員の交流企画は、すべて中止になってしまいました」
そう振り返るのは、山中里絵さん。パルシステム生活協同組合連合会に連なる生協の中でも、オンライン産地交流を先がけて開催した、パルシステム東京・産直推進課のメンバーだ。
学生時代から都会と農村をつなぐ仕事を志望してきたという山中さん。2018年に念願かなって同課に配属されてから、積極的に産地・生産者や組合員とコミュニケーションを図り、産地交流の活動に力を注いできた。
「『産地に行けない!』悔しい思いをしていた2020年の夏ごろに、課内で提案されたのが、オンライン産地交流でした。顔を合わせて、同じ空間と時間を共有するのが交流の意義。現場での体験と交流に勝るものはないと考えていた当時の私は、オンラインでの産地交流に抵抗を感じたことを覚えています」

パルシステム東京の山中里絵さん
産地交流の本質的な価値を知るからこそ、山中さんのかっとうは大きかった。しかし、ほかに方法がなかったのもまた事実。「少しでもできることを」と、オンライン産地交流の実現に向けて動き出した。
産地・生産者が背中を押す
とにかくまずは産地の生産者へ思いをぶつけようと、電話を手にした山中さん。期待と不安がないまぜになった打診に、返ってきたのは予想外の反応だった。
「『オンライン、やりましょう!』と、どの産地・生産者さんも前向きな返事をしてくれたんです。2020年にオンライン交流を企画できた産地はすべて、これまで現地での交流経験があるところ。築いてきた信頼関係を感じ、うれしくなりました」
中継は青果・米部門の担当者たちが機材の準備、当日の配信までを全面的にサポート。専門外でも、すべては交流のためと、部門も組織もまたいで力を合わせた。
それでも、難航した。

青果・米部門の担当者らが現地入りし、声をつないだ
「初めての配信は、3か所の産地をリレー方式でつなぐという難易度の高いものでした。中継先が山の中だったため、生産者さんの音声が途切れ途切れになってしまったり、トラブルを恐れて一方的に情報をお伝えする内容になってしまったり。たくさんの課題が見えました」
初回こそ実験的な運用だったが、回を追うごとに改善を重ね、完成度を上げていった。
オンライン産地交流を開催した産地の一つポークランドグループの豊下勝彦さんは「うちの農場は外部の菌を持ち込まないようにするため、どうしても見学場所に制限がでてしまう。せっかく来てもらっても、なかなか豚舎の奥の奥までは見せられなくて」と、歯がゆさを感じていたという。

オンラインでの取材に応じる豊下勝彦さん
オンラインという方法ができたことで「今回、豚が土を掘って豚舎でくつろぐ、みなさんに見せたくてもなかなか見せられなかった、豚本来の姿をライブ映像で届けられました。ポークランドの原点を見てもらえたようで、なんだかうれしかったです」(豊下さん)

ふだん入れない豚舎も、オンラインだから公開できた
オンラインでの交流は他県の会員生協にも広がっている。例えば「パルシステム新潟ときめき」が主催したのは、なんとオンラインでの豆腐作り。事前に豆腐の材料をセットにして参加者に届け、豆腐作りを体験してもらいながら、商品説明も行うというものだ。
当日作り方を教えてくれた(株)ささかみ・安中裕明さんは「現地での交流だと、一度に数十人と向き合うこともしばしば。距離は近いけど、一人一人とは心理的に遠い気がしていたんです。逆にオンラインだと、距離は遠いけど、一人一人とお話しができているような、心理的に近い感覚があって新鮮でした」
「実際に手を動かしながら聞いてもらうことで、参加者の皆さんも納得感を持って聞いてくれているようにも感じました。また、ぜひやりたいですね」

オンラインで作り方を聞きながら、各家庭で豆腐を作った
ほかの会員生協や産地が手がけたオンライン産地交流にも、身を乗り出したくなるような工夫が凝らされた。オンラインでのぶどう収穫体験や、事前に届けたお米を炊いてもらい、おにぎりを握って一緒に食べるものなど、毎回が手探りであっても、交流に手応えを感じているようだ。
「やっていく中で、産地も、参加者も、パルシステムも、みんながそれぞれ知恵を絞り、リアルタイムで交わることの意味と価値、そしてもっと伝わる相互交流の可能性を模索してきました。その意識は、準備から会が終わるその瞬間までに、今までにない一体感を生み出せたような気がするんです」(山中さん)
抱えていた産地交流の課題
実は、オンライン産地交流が始まる前から、パルシステムは産地交流に大きな課題感をもっていた。
産地へ足を運べる組合員は、多くても一度に30人ほど。一度産地に行くと、その地や生産者への思い入れが生まれ、毎年のように申し込む組合員も珍しい存在ではない。

北海道根釧地区で開催された「産地へ行こう。ツアー」の様子(2019年7月)
それは嬉しいことなのだか、交流活動のすそのを広げていくため、未経験の組合員にもできるだけ多く参加してもらいたいというのも、運営サイドの本音としてある。
つまり参加できる人数が、希望者に追いついていなかったのだ。
さらに、組合員の数が年々増加してきたこともあり、生協とは?産地交流とは?といった活動の意義が十分に伝えきられず、旅行感覚で申し込む組合員も増やしてしまったという反省もあった。
「もどかしさを感じていました。それは産地も同様だと思います。だからこそ今は、一度にたくさんの方とつながれる、オンライン交流という新しい選択肢に、可能性を感じています」(山中さん)
オンライン産地交流があぶり出した価値
「富良野青果センター」で開催された産地交流会とオンライン産地交流、両方に参加した組合員の小倉祥子さんは、それぞれに別の価値を見いだしていた。
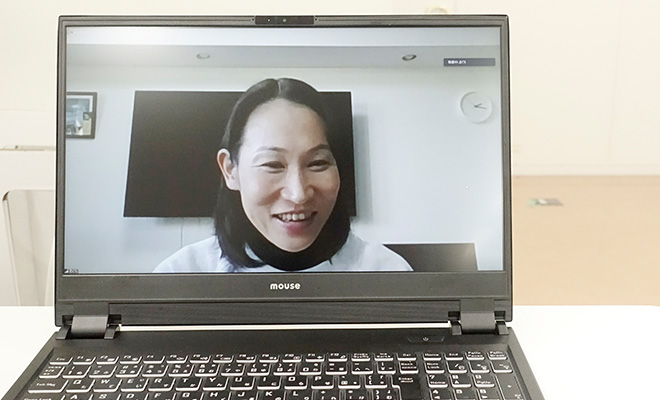
組合員の小倉祥子さん
「2019年に参加した現地での体験は、頭で知るのと実際に目にするのでは全く違うということを体感しました。とくにショックだったのが野菜の選別の様子。こんなにきれいな野菜まで出荷できないの!と驚くと同時に、間近で子供たちに見せることができたので、野菜のありがたみを感じてもらえる本当にいい機会でした」
一方で、今年度同産地のオンライン産地交流に参加した感想を聞くと、意外な答えが返ってきた。
「現地を訪ねると、子供も大人も珍しい虫や生き物に目を奪われてしまったり、風景に見とれたりと、誘惑がたくさん。振り返れば、大事なことを見落としてたことも多いように思うんです。オンラインの映像を駆使した説明だと、生産者さんが伝えたいこと、私たちが知りたいことが、もれなくダイレクトに伝わってくる感じがあって、非常にワクワクしました」

富良野青果センターでの草取り。空からでなければこの景色は見えない
「現地での交流は、知らない場所に行く感動。いわば、非日常なんですよね。産地に行ったあとは、『この産地の野菜が食べたい!』という思いが強くなりました。対して、オンライン産地交流は、気軽に見られて、日々の生活、日常の中に産地が入ってくる感覚がありました。参加したあとは、どの産地さんも今も頑張って野菜を作っているんだな、と、訪れた産地以外にも思いをはせられるようになったんです。野菜を介して、いろんな産地・生産者さんといつもつながっている感覚が芽生えました」
もちろん、いいことばかりではない。
「リアクションがすぐに返ってくるわけではないので、思いが十分に伝わっているのか、という不安な声が、産地からも参加者からもありました。現場の空気感が伝わらない分、動作や表情、声色でも伝えるようにと努力しましたが、まだまだ課題です」と山中さん。
コロナ禍でみえた交流の未来
新型コロナウイルスが、今後どのような状況を作り出すのか、予想できないところは多い。しかし、現地での交流がなくなることはないと山中さんは断言する。
「小学生にバケツなどで米作りを体験してもらい、お米についての理解を深めてもらう『お米の出前授業』で講師をしていた時、ある小学生に言われた言葉が衝撃的でした。手が汚れるのが嫌だったのか、『こんな体験しなくても、お米なんてお金で買えるじゃん』そう言われたんです。
食べ物はだれかが作っているものではなく、お金で買うものという認識だったんです。食べ物がいつ、どこにでもあたり前にあり、手に入る都市部では、食べ物をつくる現場をほとんど見る機会がありません。だから何かのきっかけがないと、作り手のことを考える機会はなかなかないと思うんです。産地交流はそのきっかけづくりの場だと思っています」。

「お米の出前授業」の様子
「『御坂うまいもの会』とのオンライン産地交流での、代表の雨宮政彦さんの一言が忘れられません。『どんな形であれ、交流を止めないことが大切なんだ』と」
産地交流歴30年以上の歴史をもつ雨宮さんの言葉に、いままで積み上げてきた「顔の見える関係」の重みを感じたという山中さん。

「御坂うまいもの会」の雨宮政彦さん
オンラインで、現地で。交流の手段は、大きな問題ではなく、どんな状況下でもそれを止めないこと。立場を越えてどうすればいいかを一緒に考えていくこと。
コロナ禍という試練によって見いだされたのは「顔の見える関係」の、ゆるぎない強さだった。




