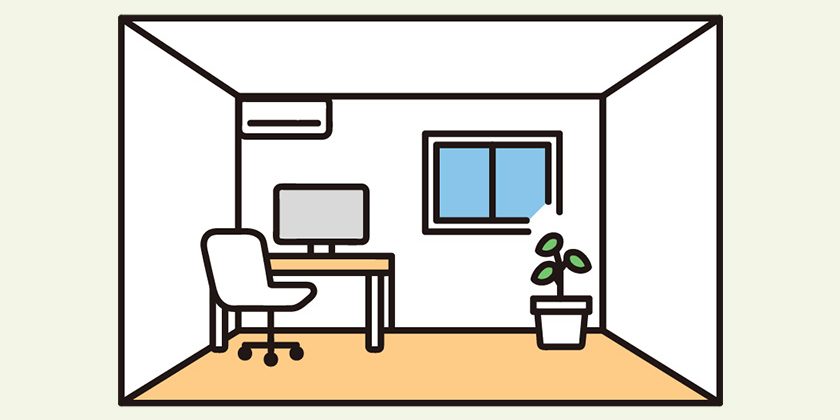空き家は増えている一方、入居を拒否される人がいる矛盾
2023年2月、滋賀県守山市の公共施設の一角で開催された交流会には、地元の福祉法人の職員や不動産業を営む経営者などが多数、集っていました。交流会の名は「居住支援に向けた活動交流会」。主催は全居協(一般社団法人全国居住支援法人協議会)です。
「全居協では、関連省庁と自治体に協力を求めながら、居住支援法人[1]の立ち上げや居住支援事業の運営、地域連携に対するアドバイザーを派遣する事業を行っています」と語るのは、全居協の事務局を担う、一般社団法人くらしサポート・ウィズ[2]の専務理事、中根裕さんです。

交流会で司会を務める中根さん(写真=編集部)
「単身高齢者やひとり親世帯、低所得世帯などは家賃滞納の不安や保証人の不在などの理由で入居を拒まれることが少なくありません。一方で空き家・空き室は全国的に増えています。そのミスマッチを解消するため、2019年に設立されたのが全居協なのです」
2017年10月に改正された新しい住宅セーフティネット法(「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」)では、住宅確保要配慮者[3]への入居相談や生活支援を担う居住支援法人が、法的に位置づけられました。
すでに法改正から約6年が経過しようとしていますが、その間に居住支援法人数は全国で687(令和5年4月末現在)となり、不動産、福祉関係など様々な法人が居住支援法人の指定を取得しています。
しかし、全国の自治体は約1,700。少子高齢化や経済的な格差が広がるなかで、居住支援法人の指定数は「まったく足りていない。居住支援法人や、自治体、不動産関係団体、福祉系団体の連携は全国的に急がれる取り組み」(中根さん)というのが現状。守山市での「交流会」は、全居協がすすめる「マッチング」のワンシーンだったのです。

社会福祉法人慈惠会の理事長、廣田さん(写真=編集部)
介護事業者には見えていなかった「住むところがない人たち」の存在
その交流会の場に、実際に居住支援法人に挑戦中の廣田岳尚(たけひさ)さんがいました。廣田さんは地元で介護施設を複数運営する、社会福祉法人の理事長。当初、住宅確保要配慮者については「まったく見えていなかった」と言います。
「言ってみれば、私たちが運営している介護事業は“生活が安定している方々”が対象者なんです。住むところさえない、住むところを探すこともままならず、住み替える先もない、という方々が実は地域にたくさんいらっしゃると知って衝撃を受けました。それを知るきっかけをくれたのは、うちのベテラン職員だったんですけどね」
そのベテラン職員とは、同じ福祉法人内で地域包括支援センターの所長を務める山本香織さんです。
「地域の高齢な方々の住み替えがままならず、終の棲家としては施設しか選択肢がない。あるいは現在、月に3~4万円ほどのアパートで細々と暮らしていらっしゃる方は施設に入るお金さえない。そんな袋小路な状況にすごく危機感を抱いていたんです。そこに居住支援法人になるためのアドバイスをしてくれる組織があるぞ、と知りまして。それで理事長を口説いてエントリーすることになったんです」

地域包括支援センター所長の山本さん(写真=編集部)
福祉と不動産が手を取り合う
「はじめは居住支援って何? 住宅セーフティ? とか訳のわからないなかで手探りで始めたような状態で」と、当時の不安な日々を思い出す廣田さん。しかし、全居協の研修会や交流会に何度も足を運ぶうちに「これはうちでもなんとかできるかもしれない」と思うようになったといいます。
「私たち介護サービス事業はずっとその業界の中でしか動けていなかったんだ、ってことに気づいたんです。自分たちだけでなんとかしようとしていた、というか。この居住支援の取り組みは地域で一体となって取り組まないと全然形にならんぞ、という確信を持ちました」
加速する少子高齢化のなかで、施設をどんどん作ればいい、という従来の「箱もの」の福祉政策ではもはや事態は改善しなくなっています。一方、人口減や格差の増大で不動産業界のマーケットは先細りが目に見えています。だからこそ「福祉と不動産が手を取り合うことが重要」と言うのは、全居協の共同代表、奥田知志さんです。
奥田さんは「“家がない”ってことは3つの危機を意味しているんです」と言います。
それは「生命の危機」「社会的な危機(制度や手続きがない)」「つながりの危機(縁の喪失、孤立)」。
困窮している人の中には、精神的な障害があったり、自立した生活を送ることが困難な人も少なくありません。
「だから、見守ってくれる人、サポートしてくれる人の存在は絶対必要。支援に必要なのは“ハウス”じゃなく“ホーム”なんです」
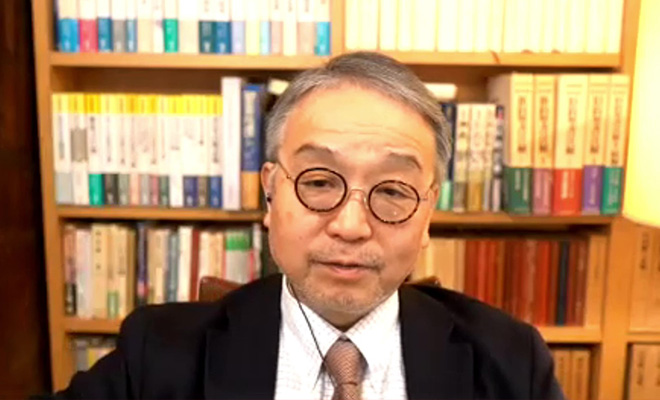
全国居住支援法人協議会共同代表、奥田さん(写真=編集部)
「家族」への押し付け
奥田さんによれば、「居住」の課題を前に大きく立ちはだかっているものが2つある、とのこと。
ひとつが「家族という存在」。
「これまでの日本の社会保障制度は、家族の支えを前提に考えられてきました。両親ともに健在で、家族関係も家計も安定していればそれもよいでしょう。しかし、そんな余裕が経済的にも精神的にもある人はほんの一握りです。これまで家族主義的だった企業の終身雇用システムもほぼ終わろうとしています」
家族も企業も脆弱化して、人を支えるしくみそのものが崩れてしまった、それが今なんです、と語気を強めます。
かつて炭鉱の閉山や製鉄所の縮小で地域の活力がなくなり、野宿者が増えていた北九州で長年、ホームレスへの炊き出しや自立支援のボランティアを行ってきた奥田さん。その活動(NPO法人抱樸)は設立から30数年を迎え、今では半年間の自立プログラムを通じて9割を超える人が自立できるようになっている、といいます。
だからこそ「しくみを変える。そこにメスを入れるのが秘訣なんです」と奥田さん。

交流会では活発にネットワークづくりが行われる(写真= 編集部)
家族の機能を社会化する
そして、もうひとつ立ちはだかるものが「縦割り行政」。
厚生労働省の福祉分野の枠組みでは、養護施設や老人福祉施設、医療施設などの「施設」で受け入れるか、自宅にいながら通所施設に通うかの選択になるため、「施設に入れず住宅のない人」へのケアが困難。一方、生活困窮者が住宅を借りられない実態を把握しているのは、国土交通省の住宅分野となっていました。
そんな省庁や部署ごとの縦割りな構造がその弊害となってきましたが、改正住宅セーフティーネット法では、国交省の政策であるとともに厚労省や法務省の対象者やニーズも意識されています。省庁や官民を超えた議論が、これからの制度の可能性を広げていくとも言われています。
「この法律で居住支援法人ができ、その全国組織となる全居協が設立されたことを考えれば、志ある人たちと“縦”を崩し、つながることで解決できる課題はたくさんあるはずなんです」
これまで家族が担ってきた機能をいかに社会が担えるか――「家族の機能を社会化すること」の重要性を説く奥田さん。
全居協とともに、居住支援法人が各地域に広がっていくことで、ひとりでも多くの人が「ホーム」を得られる社会になっていくためにも、私たち一人ひとりのマインドセットも迫られているのかもしれません。
「トータルでいろいろな制度や政策、地域の資源を引っ張ってきて、“この人に対する居住の支援はこれなんだ!”と言い切れるプランニングができるプレーヤー、それが居住支援法人であり、そのしくみを応援していくのが私たちのできる最良の地域貢献ですね」(奥田さん)