ようやく軌道に乗った矢先に起きた原発事故
阿武隈山系の一角、福島県相馬市玉野地区で、原木しいたけ栽培を手掛けている工藤義行さん。もともと農林水産省の職員だった工藤さんは、16年前に早期退職して50代で就農し、念願だったきのこ栽培を始めた。干ししいたけをはじめ、なめこ、ひらたけなどを地元の農協や直売所に販売。四季の変化に富んだ玉野の気候が栽培に向き、「工藤さんのきのこがほしい」と指名するファンもつくようになっていたという。
生産も軌道に乗り始め、これから規模拡大を……と意気込んでいた矢先に起きたのが、東日本大震災だった。原発事故で状況は一変。市全域で原木しいたけの出荷が制限され、工藤さんは山に置いていたしいたけ3トン分のホダ木(原木にしいたけの菌を植えたもの)約2万本をすべて廃棄しなければならなかった。
「落ち込んでいるわけにもいかないから、秋田や長野から取り寄せた原木を使って、出荷制限のかからないハウス栽培を再開しましたが、地元の木とはどうも勝手が違うんですよね」と工藤さん。「震災前は小中学生の自然体験学習を受け入れていたんですが、それもできなくなっちゃって……」と、悔しそうに話す。

「山で作るきのこは本当にうまいんですよ」と、栽培の再開を切望する工藤義行さん(写真=深澤慎平)
原木の名産地・阿武隈山系は、7年間手つかずのまま
原木しいたけは、栽培にコナラやクヌギなど樹齢20~25年の広葉樹を使う。山が紅葉し始めた頃から春の新芽が出るまでの期間に伐採し、乾燥させて90cmに切断。1本につき30~60前後の種菌を植え付けて、ホダ木の栄養分だけでしいたけを育てる。
植菌から収穫までは早くても1年。きめ細かな温度・湿度管理が欠かせず、5~10kgもある原木を並べたり運んだりと大変な労力を伴う仕事だ。近年では、農家の高齢化もあり、オガクズなどを敷いたポットで効率的に育てる菌床栽培が市場の9割を占めているが、「原木しいたけは、うまみや香りが格別」と、こだわりを持つ生産者も多い。

試験栽培中のしいたけ。木の持つ養分だけで育つ原木しいたけは、まさに自然の恵みだ(福島県相馬市・写真=深澤慎平)
震災前、原木しいたけを栽培する農家向けに県をまたいで出荷される原木の5割以上を占めていたのが福島県産だった(※1)。中でも広葉樹林を主体とする阿武隈山系は、比較的なだらかな地形で気候も穏やかなため、木質が柔らかく、昔から原木の名産地として知られていた。
ところが、原発事故後、福島県の山林からの原木供給は止まったままだ。しいたけの放射性セシウム濃度の基準値が100ベクレル/kgに設定されたことに伴い、原木の指標値も、そこから発生するしいたけが基準値を超えないと見込める50ベクレル/kgに定められている。
「このあたりの山々も、7年間、手つかずで放置されているんです」と工藤さんはため息をつく。
※1:しいたけ原木の調達ルート・他県等からの調達内訳(2010年特用林産基礎資料)

樹齢20~25年のコナラやクヌギは原木に最適(福島県相馬市・写真=深澤慎平)
茨城の原木しいたけも存亡の危機に
原発事故で大きな痛手を被ったのは、福島の生産者だけではなかった。原発から150kmの位置にある生協パルシステムの産直産地・JAつくば市谷田部産直部会(茨城県つくば市)の原木しいたけ生産者も、事故の後から目に見えない放射能との闘いが始まった。
産直部会のメンバーで、栽培歴50年という飯泉孝司さんが震災に見舞われたのは、2011年分として入荷した原木への植菌が終了し、作業が一段落ついてたときだった。ホダ木が崩れた作業場の片づけに追われる最中に放射性物質の拡散の知らせを受け、愕然としたという。
しいたけの基準値が暫定の500ベクレル/kgから100ベクレル/kgに下げられた12年4月には、自主検査で出荷前のホダ木から基準を超える数値が検出され、そのホダ木をすべて廃棄せざるを得なかった。経験したことのない事態に、「精神的に最もきつかった」と話す。

震災当初、自主的な廃棄も迫られた(茨城県つくば市・JAつくば市谷田部産直部会)
「正直、廃業という言葉が頭をかすめた時期もありました」と飯泉さん。「ただ、周囲の生産者がことごとく販売先から取引を停止されるなか、パルシステムは、放射能対策や検査に関する情報提供や協力など、我々と共にこの問題に向き合ってくれた。当時、注文数は半分くらいに減ってしまったけれど、生産し続けられたことで救われました」と振り返る。
「この7年間、考えられる限りの放射能対策を尽くしてきた」と飯泉さん。
原木の汚染をできる限り軽減するため、当初は、機械メーカーと共同で開発した高圧洗浄機で原木を1本1本洗浄(※2)。雨や空気中からの汚染を防ぐためハウス型の人工ホダ場を建設したときには、地面をはいで土をすべて入れ替えた。原木仕入れにおいては、指標値以下でもできるだけ低い数値のものを調達。原木は入荷ロットごとに管理し、基準値を超えるしいたけが一つでも出たら、同じロットのしいたけをすべて処分してきた。

雨や空気中からの降下による汚染を防ぐために、ホダ場ハウスの中で栽培を行っている(茨城県つくば市・JAつくば市谷田部産直部会)
「パルシステムとも連携して検査体制をとり(※3)、とにかく、基準値を超えるものを絶対出さないように細心の注意を払ったことで、つくば市は出荷制限を免れたんです。でも、県内には今も出荷制限・自粛措置がとられている市町村が17もある(※4)。国から解除に向けた生産のガイドラインも示されていますが、非常に細かな管理事項が決められており、クリアするのは容易ではありません。これからも農家の廃業は続くと思います」
※2:当初は洗浄により放射性物質減少に大きな効果があったが、現在は放射性物質が原木の内部に入り込み、外皮の洗浄では効果が見込めないため中止している。
※3:JAつくば市谷田部で、ロットごと出荷前に検査。出荷された後は、組合員への供給前に毎週5パックをジーピーエスで検査。さらにパルシステムの商品検査センターでも、高性能のゲルマニウム半導体検出器で毎週検査し(下限値:3ベクレル/kg)、検査結果を公表している。
※4:きのこや山菜の出荷制限等の状況(茨城県)
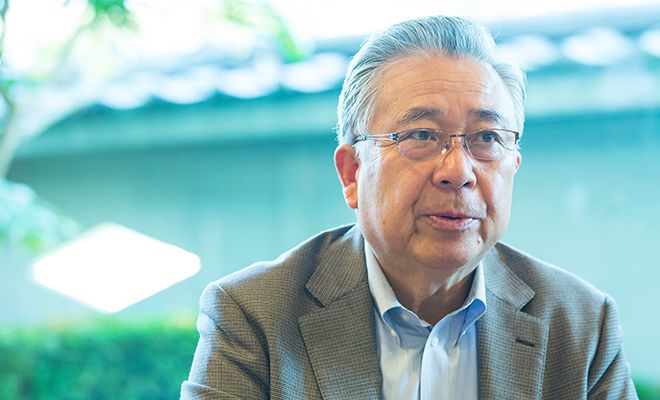
原木しいたけを作り続けて50年。「これが最後の仕事」と里山再生に寄せる思いを語る飯泉孝司さん(写真=深澤慎平)
原木の調達コストは2倍に
放射能対策に膨大な時間とコストを費やしてきた飯泉さんは、「最善の放射能対策は、汚染度の低い原木を使用すること」と確信する。
事故当時約0.1マイクロシーベルト/時に上昇したつくば市の空間線量は、約0.03マイクロシーベルト/時と事故前と変わらない数値まで下がり、栽培中の汚染のリスクは大幅に減った。だからこそ、いまだに改善の目途が立たない原木の供給体制にもどかしさを隠せない。
林野庁は、有識者、生産・流通関係者などからなる「きのこ生産資材安定供給検討委員会」で、原木産地の掘り起こしや需要者と供給者のマッチングを図ってきたが、状況は好転していない。

JAつくば市谷田部産直部会では、原木を産地ごとに番号付けして管理。すべてのロットごとに、しいたけの放射能検査を行っている
「震災前、うちで使っていた原木のほとんどが福島産でした。今は、主に長野、埼玉(秩父地域)、大分から仕入れています。数量は事故前の8割近くまで回復したのですが、入荷の時期も遅れがちですし、木の質と菌種との相性もまだ見極めきれません。最近、しいたけの病気に悩まされているのですが、それも原木の質や植菌の時期のずれによるものかもしれません」
原木価格の高騰も深刻だ。飯泉さんの場合、震災前に比べ調達コストは2倍近くに跳ね上がっているという。
「県から原木購入の補助金が出ていることもあって、価格を釣り上げる業者もいるんです。質の良い原木を求めて、争奪戦も激しくなっている。しかも、補助金は2020年までの予定ということで、その先の見通しが立ちません」と不安を隠せない。
「俺たちで、原木林を取り戻すしかない」
「安心して使える原木を手に入れるためには、やはり、山を除染して木を植え直すしかないのでは」と考えた飯泉さんは、2013年、パルシステムなどの消費者団体や種菌メーカー、研究者などとともに、NPO法人「里山再生と食の安全を考える会」を立ち上げた。
「最初は、東京電力に『原発事故で汚染された原木林を再生するための研究をするから基金を出してくれ』と掛け合ったのですが、返事は『NO』。それなら、自分たちでやるしかないと腹をくくり、賛同者を募ったのです」
同NPOでは、まず茨城県の里山再生事業を請け負い、県内の山林の伐採、除染に着手。また、地元のつくば市では、子どもたちの森林体験やグリーンツーリズムの拠点となるような森づくりも手掛けている。長年放置されていた約5haの山林を、伸び放題だった下草をきれいに刈って整備し、コナラや桜などの苗を約3000本植樹。地元の市民も巻き込んで、20年後には原木林としてよみがえらせることを目指すという。

「原木しいたけを絶やしたくない」と率先して森づくりに取り組む若手きのこ生産者たち(茨城県つくば市・JAつくば市谷田部産直部会)
パルシステムが同NPOに参加する理由について、「これまでも“産直”の取り組みを通して、常に組合員と生産者とで課題を共有してきましたから」と語るのは、株式会社ジーピーエス(※5)事業本部長・工藤友明さん。「今回の原発事故の影響を乗り越えていくためにも、放射能の数値が低い食品を生産者に一方的に求めるのではなく、安心して口にできる食を手にするために自分たちには何ができるかを、消費者もいっしょに考えていくことが必要だと思います」
※5:株式会社ジーピーエスは、パルシステムグループの産直青果や米の仕入れ、品質管理、物流を担う専門子会社。

「福島の里山再生のために、自分自身にできることを考えたい」と語る工藤友明さん(写真=深澤慎平)
10aの実験林を、福島の里山再生の一歩に
同NPOは、2017年、福島でも山林の再生活動に取り組み始めた。
「原発事故の最大の被害者は、福島の自然と福島の人々。この事実は決して風化させてはいけない」(飯泉さん)と、6月に、玉野地区の工藤さんが自力で皆伐した10aの土地に、有志で約200本のクヌギの苗を植樹。将来的にしいたけの原木として利用することを目指す(※6)。同時に、国立研究開発法人森林研究・整備機構「森林総合研究所」と東京大学大学院農学生命科学研究科の協力を得て、原木の放射能低減の手法を開発するための実験もここで行っている。

放射能低減実験が行われている相馬市玉野区の一画。定期的に手入れをし、原木林としてよみがえらせることを目指す(写真=深澤慎平)
「土を天地返しした区域、天地返ししていない区域、放射性セシウムの吸着を抑制するといわれるカリウムを施肥した区域、施肥しない区域に分け、区域ごとに植えた木の放射線量をモニタリングしています。セシウム137は100年でようやく10分の1に下がるといわれていますが、皆伐と植林を繰り返すことで、より短期間で減衰できるのではないか――それを実証する実験です」と、飯泉さんは期待を寄せる。
※8:同NPOの活動は、パルシステム連合会の「地域づくり基金」の助成を受けている。

採取されたクヌギの葉。実験区域ごとの放射性物質の数値を比較し、放射能低減効果を探る(写真=深澤慎平)
人の手で守られる里山。原木しいたけの価値を考えたい
原発事故以降、自らが、原木を通して里山とつながり、その恩恵である食べ物を通して消費者とつながっていたことを改めて感じるようになったという飯泉さん。
国土の7割を森林が占める日本では、昔から人々のくらしは豊かな森や山の恵みとともにあった。木々は根を張り巡らせて土を固定し、落ちた葉が土を肥やして多様な生物の命を育む。定期的に伐採して木々を若返らせることが、里山生態系の持続的な循環には不可欠で、そんな循環の一角を担ってきたのが、原木しいたけをはじめとする里山の仕事なのだ。

里山の恵みに生かされてきた暮らしを取り戻すまで、人々の挑戦は続く(福島県相馬市・写真=深澤慎平)
「日本の原風景の一つ、秋の紅葉も、人の手が入らなければ枯れ山ばかりで見られなくなってしまう。原木しいたけは、日本の風土や文化をつないでいく仕事なんだと自慢していい」と胸を張る飯泉さん。
「山が好きで原木しいたけを栽培していきたいという次の世代のためにも、それができる環境を整えておいてあげなきゃ。東日本の原木しいたけをこの先も守っていけるかどうか、今が正念場なんです」――前を見据えてそう語る表情に、原木しいたけに生涯をかけてきた農業者としての覚悟が見える。




